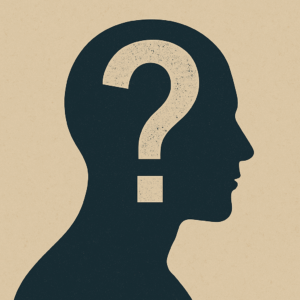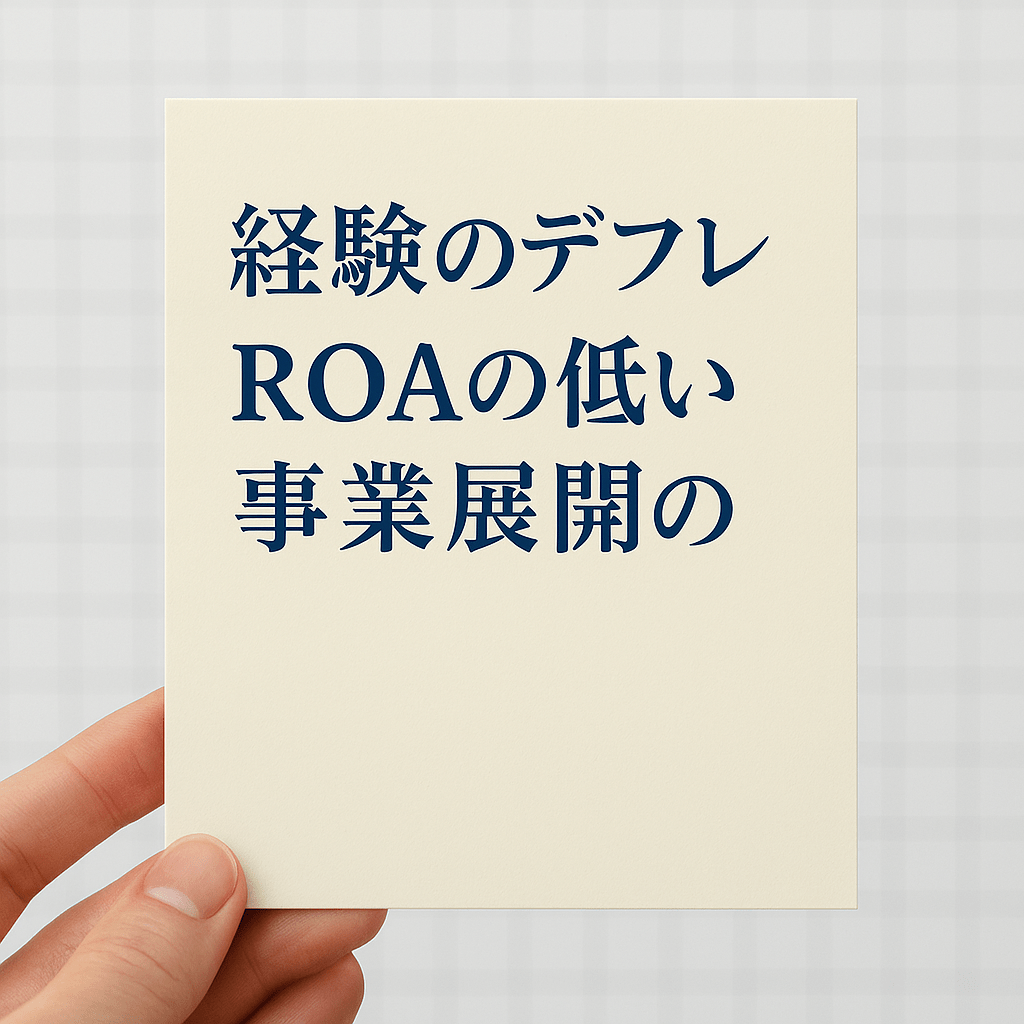
経験のデフレとROAの低い事業展開──なぜ「資産」は成果を生まないのか?
形式的な経験が積み重なる一方で、組織や個人の資産が十分に活かされていない──こうした「停滞の構造」は、現代の働き方や事業運営に深く根を下ろしています。本記事では、「経験のデフレ」と「ROAの低下」が密接に関連している理由と、それをどう打開するかの視点を提示します。
「経験のデフレ」とは何か?──資格・年数の“空洞化”
現代社会において、経験とは「キャリアの蓄積」や「履歴の厚み」として語られがちです。しかし、その中身がともなわなければ、経験は“重み”ではなく“ノイズ”になってしまいます。
例えば以下のような構造が、多くの現場で見られます。
- 資格取得や研修受講が目的化し、実務や応用に接続されない
- 異動や昇進はあるが、内面的変化や主体性を伴っていない
- KPI・OKRの達成に追われ、本質的な思考や行動のトライアルができない
これはつまり、「見た目の経験が膨らんでいるが、内実の意味や統合が欠けている」状態です。いわば、**“経験のインフレ”に見せかけた“デフレ”**。
こうして生じるのは、「成長している気になっているが、何も変わっていない」不全感です。
ROAの低い事業展開とは?──「広げるが、回収しない」日本的経営の構造
ROA(総資産利益率)は、企業の持つ資産に対してどれだけ利益を生み出しているかを示す重要な指標です。しかし、日本の多くの企業では、この数値が慢性的に低い状態が続いています。
典型的な構造
- 多拠点・多機能展開によるコスト増(人件費・設備費)
- 「過去の成功体験」への執着からの過剰な温存と延命
- 本業以外の分野への資源分散と、シナジーの不発
結果として、「資産は積み上がっているが、活かされていない」状態が常態化しています。つまりこれは、**経験のデフレ構造と極めて類似している**のです。
両者の共通点──学ばない構造の温床
「経験のデフレ」と「ROAの低さ」は、一見異なるテーマのようでいて、実は以下のような共通構造を共有しています。
意味づけされていない経験(=内省なき反復)
+
戦略なき資産運用(=意志のない投資)
=
学習・成長・成果が結びつかない停滞
つまり「動いているが、進んでいない」「積み上がっているが、変わっていない」といった“形式主義のワナ”です。
打開の方向性1:経験を「再資産化」する
1. 意味化と物語化
経験は、単なる出来事の羅列ではなく、意味づけによって価値が生まれます。たとえば、失敗したプロジェクトも、「なぜそうなったか」「自分はどう変化したか」を言語化すれば、戦略的思考や判断の糧となります。
2. 振り返りと対話による統合
- 定期的な1on1やレビューを“経験の内省”として機能させる
- 個人・チーム単位での「暗黙知」の共有とドキュメント化
3. 感情のレイヤーを取り戻す
経験の中に含まれる“感情の軌跡”──違和感、怒り、共感など──を丁寧に掘り起こすこと。それは戦略と創造性の原資になります。
打開の方向性2:ROAを“数字”から“構造”へ読み替える
1. 投資先を「自社資産」と「未来価値」に限定する
- 過去の惰性ではなく、「意味」や「学習」が生まれる領域へ資源集中
- 人的資本・ナレッジ・関係資本の回収可能性を設計に含める
2. 非財務資産のROAを意識する
たとえば「理念への共感」や「顧客の納得感」といった、財務に直結しない資産も、長期的には高ROAを支えます。これらは“見えない資産”であり、ROA向上の隠れた鍵でもあります。
3. 意志ある撤退と、選択の強度を高める
「やめる力」は、ROA改善の基本です。漫然と続けている活動や、意味を喪失した施策からの戦略的撤退は、意志のある組織にしかできません。
問い直しのワーク:経験と資産の再編集
以下の問いを自分自身・組織のリーダーとして内省してみてください。
- 今、自分が経験していることは「意味」として統合できているか?
- どの資産(人・物・時間)が、最も活かされていないか?
- 投資しているものに、どんな「未来のリターン」があるか?
- 何をやめれば、最もROAが高まるか?