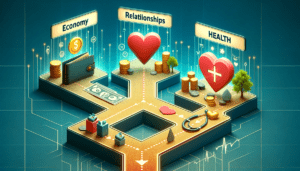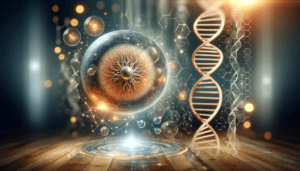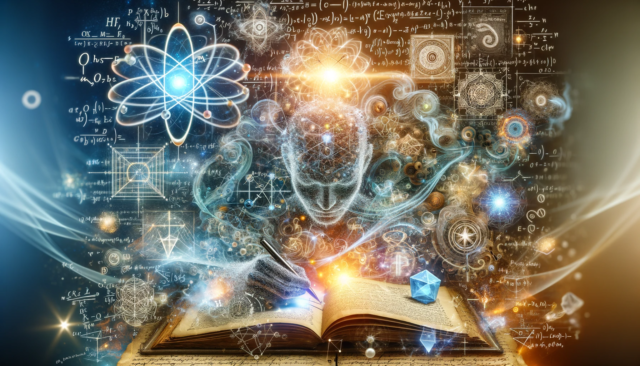
今回は、花粉症、多重人格、アレルギーといった症状と、それら全ての根底にある力との関連性について深く掘り下げてみましょう。
この探求の過程で思考が分岐することもあるかもしれませんが、その全てが我々の理解に対する貴重な足跡となるでしょう。
古代の知恵と現代の科学が交錯する、その領域は私たちが進んできた旅路の一部であり、それらはいまだに鮮やかな色彩を放っています。
古代の知恵は、自然界の全ての要素の根底には「知性」があると認識しています。
これは、たとえばDNAの存在が典型的な例証です。
地球上には約5000万種の生物が存在し、その全てがDNAを共有しています。
DNAは常に細胞内に存在し、全ての生命体が細胞から成ることを考えると、DNAが生命の基盤であることは明白です。
このことは、全ての生物が我々と繋がっており、人間はその一部であるという新たな視点を提示します。
これは人間中心的な考え方に異を唱え、新たな世界観を形成します。
この新たな視点は、古代からの知恵と重なる部分が多く、私たちはライフデザインやパーソナルデザイン研究の基盤としてそ用いることを試みています。
そして、我々が使用する技術は、生命体が持つ量子的なレベルに接触できるとするものです。
その技術を制御するためには特殊な技術が必要ですが、これによって通常の認識を遥かに超越した領域へと到達できるのです。
その領域は「静寂」であり、それは量子力学的な体に接触するための入り口であると言えます。
これが理解できるようになると、私たちは身体を単なる細胞の集合体としてではなく、知性の静かな流れとして認識し始めます。
このレベルに接触することができれば、体内のどの状態も変化させることが可能だといわれています。
たとえば、花粉症を新たな視点から見てみましょう。
花粉症は、様々な刺激、例えば花粉、気候の変化、心身の興奮状態や過労によって引き起こされると一般に理解されています。
しかし、実際のところ、人間の心の動きが反応を引き起こすとも言えないでしょうか?
造花のバラを見て花粉症の症状が引き起こされた人に、それが造花であることを告げた瞬間に症状が消える。
このような事例は、人間の解釈や認識が身体の反応に影響を及ぼすことを示しています。
多重人格に関しても、同様の現象が観察されます。
人格によって疾患が異なること、その疾患が人格の変化と連動して表れたり消えたりすること、さらには目の色が変わるなど、身体の物理的な変化が起きることもあります。
これらの現象は、身体が何らかの信号、おそらく量子レベルの信号に反応していると考えることもできます。
アレルギー反応についても同様の解釈が可能かもしれません。
一般的には、免疫系の白血球がアレルギー反応を引き起こす抗体で覆われ、これが抗原と接触すると化学反応が起きると理解されています。
しかし、多重人格者が人格によってアレルギー反応をコントロールしている事例を考えると、ここにも「選択」が存在するのかもしれません。
つまり、細胞自体が何らかの知性を持ち、アレルギー反応を起こすかどうかを選択しているのではないかと推測できます。
これらの視点から、すべての疾病は我々自身が選択している可能性があるという見方を否定することはできません。
この選択は意識レベルを超えた深いところで行われている可能性があり、それゆえに私たちはそれを自覚できないのかもしれません。
科学技術が進歩しても、我々の体の機能を完全に解明することは難しいでしょう。
しかし、この理論が正しいとすると、私たちには無意識のうちに疾患を選択する能力があり、したがって、それを制御する潜在的な能力も存在すると考えられます。
私自身もアレルギー体質と診断された時期もありましたが、この新たな視点と出会ってからは、それらしき症状が表れていないのです。
年齢の経過とともに私が鈍感になっただけなのかもしれません。
もしかすると、自身のアレルギー反応を選択、もしくは制御する能力を身につけたのかもしれません。
以上の視点を通じて、古代の知恵と現代科学が重なる部分を探り、身体と心、そして自然との深い関わりを考えることが重要だと感じています。
量子レベルの存在、つまり私たちの「静寂」の中に存在する力を理解し、それを用いることで私たちの生活、病気との向き合い方が変わるかもしれません。
人間が自然の一部であるという視点を忘れずに、その一部として、自己を理解し、自己と自然の調和を目指すことが、最終的に健康を維持し、生きていく上での智慧となるのではないでしょうか。