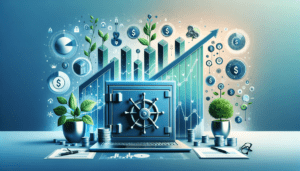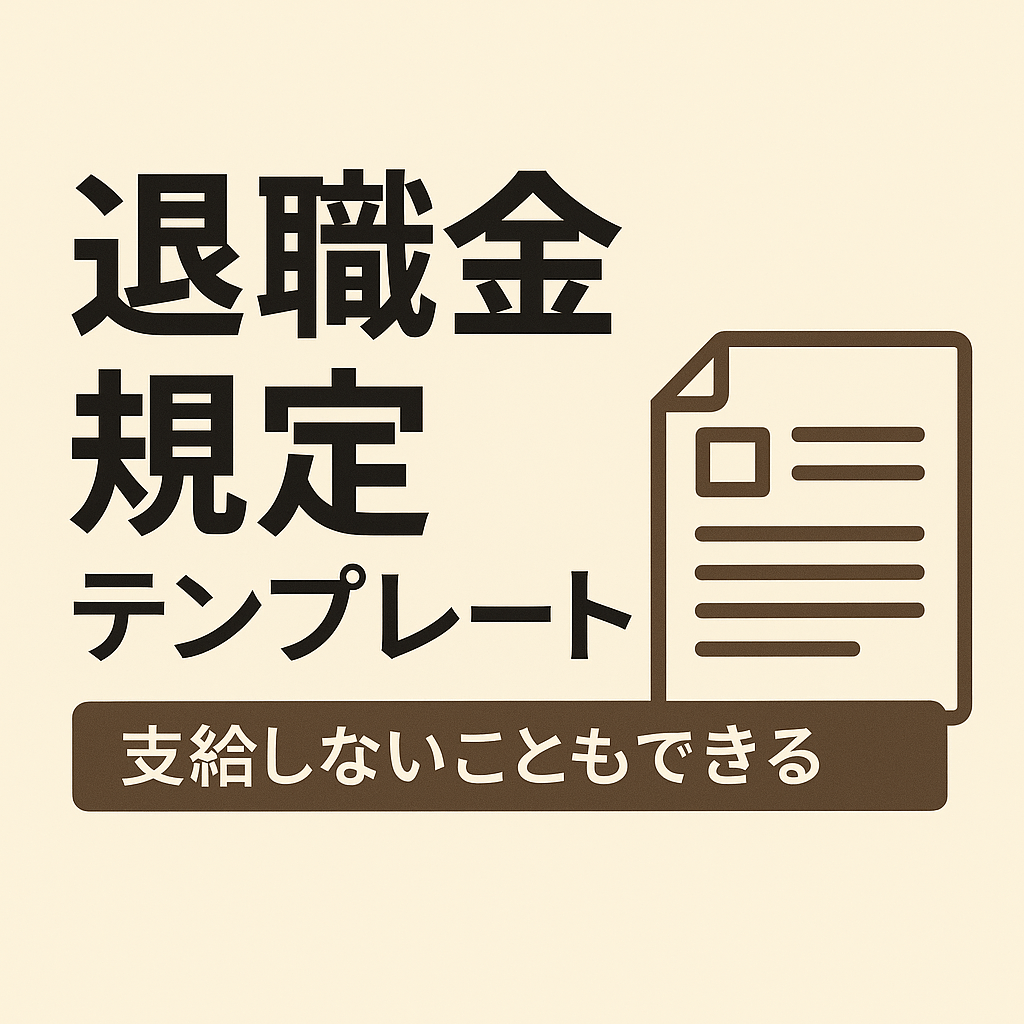
退職金制度は、社員への感謝や長年の労をねぎらう目的で導入されるケースが多いものです。
しかし、実務の現場では「退職金規定を作ったことでかえってトラブルになった」という事例が後を絶ちません。
本記事では、制度化のリスクや注意点、さらに“制度に頼らず感情的満足を得る方法”まで、実践的な視点で丁寧に解説します。
退職金は「善意」から「権利」へ変わる
退職金規定を設ける際にまず考えるべきは、「一度制度化すると、それが社員にとって“当然の権利”と認識される」という点です。
当初は感謝の気持ちで設けた制度でも、時間が経つにつれ、制度が独り歩きし、「なぜもらえないのか」「なぜあの人は多いのか」といった不満や誤解を生み出します。
これは、心理学でいう「期待値の固定化」や「認知的不協和」が働くためです。
現場で起きている具体的な問題例
- 赤字決算でも「規定通りだから払ってほしい」と主張される
- 懲戒解雇でも「規定に書いてあるから」と争いになる
- 在籍年数のみで金額が決まり、成果を上げた人が不満を持つ
- 中堅社員が「自分は退職金もらえるから辞めない」と消極的に残る
このような状況では、制度が本来の目的を果たすどころか、むしろ「不満足を製造する装置」と化してしまうことがあります。
退職金規定を設ける場合の注意点
それでもなお退職金制度を設ける必要がある場合は、以下の3点を明記しておくことでトラブルを大幅に減らすことができます。
- 任意規定とする(支給する“ことがある”)
- 不支給・減額の条件を具体的に記載する
- 会社の裁量・経営状況によって支給内容が変動する旨を記載する
トラブル回避型の退職金規定テンプレート(例)
第◯条(退職金の支給)
1. 退職金は、会社が必要と認めた場合に限り、退職者に対して慰労金等の名目で支給することがある。
2. 金額、支給方法、時期等は、在籍年数、勤務実績、会社の経営状況等を総合的に勘案し、会社が個別に定める。
3. 懲戒解雇等の場合には、退職金を支給しない、または減額することがある。
第◯条(支給の除外)
次のいずれかに該当する場合、退職金は支給しない。
- 経営状態が著しく悪化していると認められる場合
- 在籍期間が3年未満の場合
- 懲戒事由に該当する退職の場合
- その他、会社が不適当と判断した場合
このように明文化することで、制度上の義務化・権利化を回避しつつ、感謝の意を示す柔軟な運用が可能になります。
例えば:中退共を導入する際の留意点
中退共は、中小企業向けに設計された退職金共済制度で、手軽に制度を構築できるというメリットがあります。
しかし、「退職金支給が制度化・権利化される」という本質的な性格を理解せずに導入してしまうと、後に大きなトラブルに発展するリスクもあるのです。
1. 任意支給ではなくなる
中退共は、加入した時点で共済契約が成立し、掛金が支払われている限り、従業員側の「受け取る権利」が確立されます。そのため、例えば「経営が厳しいから今回は出さない」といった判断は基本的にできません。
2. 減額や不支給の自由が失われる
一般的な社内規定では、懲戒解雇時の減額・不支給、在籍年数の条件などを会社の裁量で設定できます。しかし中退共では、そのような裁量が原則として認められません。仮に従業員が問題行動を起こしていたとしても、共済契約に基づく退職金は支給義務が生じます。
3. 制度の柔軟性が損なわれる
会社独自の退職金制度では、「慰労の意味合いで支給する」などの抽象的なスタンスを取りつつ、個別の判断を可能にする余地があります。しかし中退共のような共済制度では、公平性・機械的支給が前提となるため、経営判断によるコントロールは難しくなります。
つまり、中退共は「義務化」に近い選択肢
中退共のような制度は、「制度として確実に退職金を支給したい」企業にとっては便利ですが、退職金制度をあえて任意とし、不満やトラブルを防ぐための柔軟な運用をしたい企業には不向きです。
したがって、「退職金制度を設けない」または「任意支給にとどめておく」方針を取る場合には、中退共のような制度を安易に導入せず、自社に合った規定と運用方針をじっくり検討することが望ましいと言えるでしょう。
制度に頼らない「感情的満足」の設計
一方で、退職金制度そのものを設けずとも、退職者が“納得感”や“感謝”を感じられる工夫をすることは十分に可能です。
以下は実務で効果的だった事例です。
① 慰労会+記念ギフト+感謝の手紙
金銭的価値よりも、「あなたがこの会社に貢献してくれた」という承認の言葉が心に残ります。
家族にもメッセージを贈ることで、退職者の社会的承認感が高まり、組織への良い印象が残ります。
② 功労金としての“個別対応”
制度としてではなく、社長・役員判断で個別に支給する方法です。
例えば「お世話になったからこれを」といった形で手渡すと、金額以上の感情的価値が生まれます。
③ 退職後のつながり構築(OBネットワーク)
業務委託やコンサルとして再び関わってもらう仕組みを作ることで、一度きりの退職ではなく継続的な信頼関係を築くことができます。
認知科学から見る「納得のメカニズム」
人は、金額そのものよりも「なぜそれが妥当なのか」という説明や、「自分の貢献が認められたかどうか」といった認知的評価によって、満足度が決まります。
制度によって期待が生まれ、結果がそれに届かないと「不公平感」「裏切られた感」が強まる傾向があります(認知的不協和の理論)。
その意味でも、制度よりも信頼と対話による運用のほうが、退職者・企業双方にとって持続的かつ健全な関係を保ちやすいのです。
まとめ:制度ではなく「信頼の運用」をベースに
退職金は、制度として一律に整えることが必ずしも最善とは限りません。
むしろ、制度化による「不満足の製造」を避けるために、任意・柔軟・感情価値に焦点を当てる選択肢もあるのです。
重要なのは、「金額」よりも「感謝の伝え方」。
制度よりも人と人との関係性をどう結ぶかを大切にすることで、円満な退職と信頼の継続が実現します。
退職金にお悩みの方は、まずは「制度の前提を疑ってみる」ことから始めてみてはいかがでしょうか。