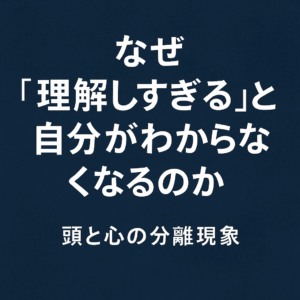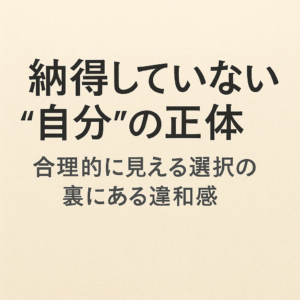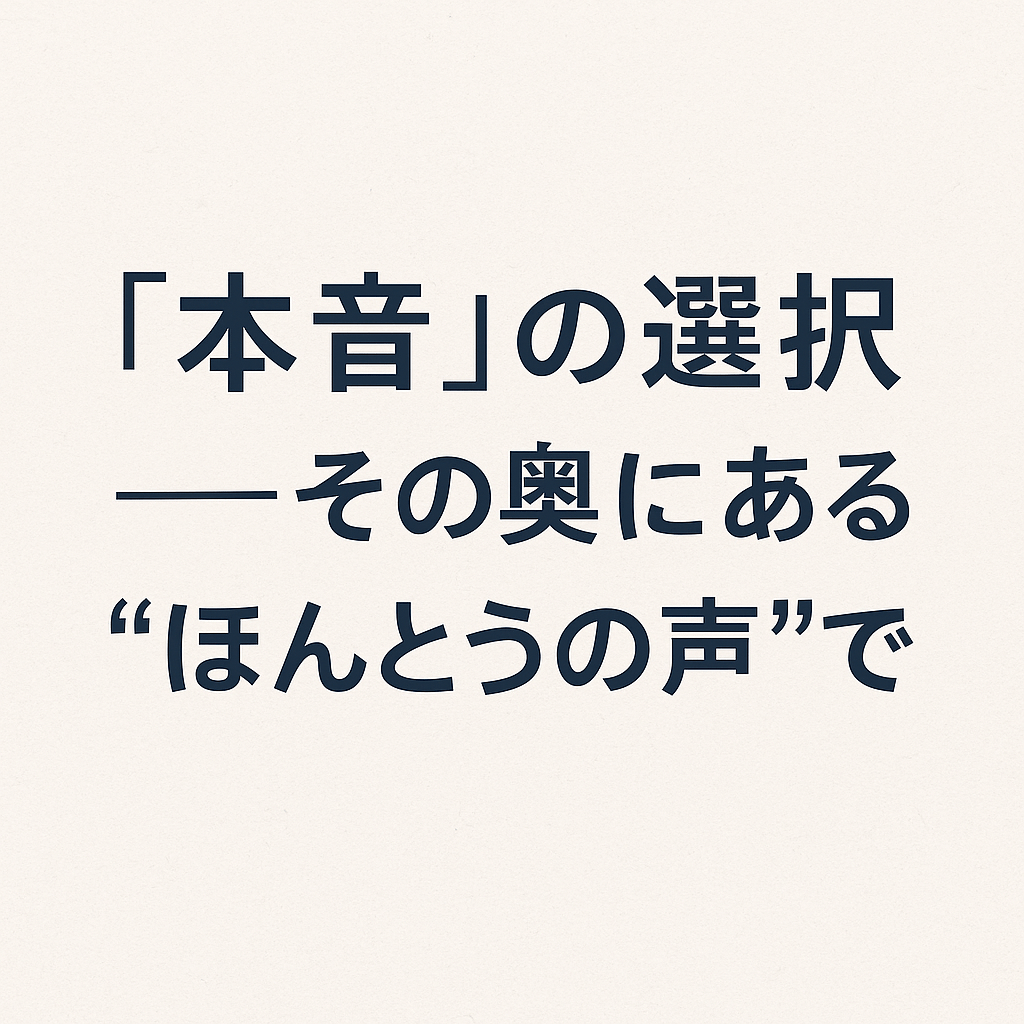
誰かに「本当はどうしたいの?」と尋ねられて、黙ってしまったことはありませんか?
あるいは、答えたものの、どこかで「それって建前じゃない?」と自分自身に問い返すような違和感を抱いたことは?
素直な気持ちがわからない。というより、「素直になること」が怖い──。
この感覚は、自己理解における見えづらい“壁”です。
私たちは無意識のうちに、自分を守るための「思考の枠組み」や「反応の型」を身につけています。
それがときに、率直な感情の表現や本音の選択を遠ざけてしまうのです。
この壁の正体を丁寧に掘り下げることで、「本当は、どうしたいのか?」という問いにもう一度向き合うための静かなスペースがひらけていきます。
第1章:「素直になれない」は、“わがまま”ではない
「素直に言えばいいのに」「もっと本音を出してみたら?」
周囲からそんな言葉をかけられて、余計に言葉を失ってしまったことはありませんか?
その場では曖昧に笑って受け流したとしても、心の奥では「それができないから苦しいのに」とつぶやいていたかもしれません。
「素直になれない」という感覚には、自分でも気づいていない多層的な背景が隠れています。
それは単なる“性格”や“わがまま”ではなく、これまでの人間関係や環境の中で、無意識に学び取ってきた「自分の守り方」の一つなのです。
たとえば──
- 「感情を出すと、面倒くさいと思われる」と感じた経験
- 「自分の望みを伝えても、どうせ叶わない」と諦める癖
- 「遠慮しないと、誰かが困る」という責任感
これらの経験が繰り返されると、「素直になる=リスク」だと心が学習してしまいます。
だからこそ、無意識に“素直な自分”を閉じ込めて、あらかじめ他者の反応を想定しながら「正解っぽい自分」を演じるようになるのです。
それは生き延びるための「工夫」であり、「やむを得ない選択」でもありました。
そしてこの“工夫”は、ある段階では私たちを守り、関係を維持するために機能していたのです。
けれど、ある時点から、それが“重荷”に変わっていく。
自分を押し殺すことに慣れすぎて、「本当はどうしたいのか」「なにを感じているのか」が自分でもわからなくなってしまうのです。
「素直になれない自分」を否定するのではなく、なぜそうなったのかに目を向けること。
それは、自分という存在への理解と尊重の第一歩です。
「素直になる」のではなく、「素直になれなかった理由」に、静かに気づいていく──
そのプロセスが、本当の意味での自己理解へとつながっていきます。
第2章:“本音”とは何か──思考と感情のあいだにあるもの
「本音がわからない」「自分の気持ちが見えない」──そんな言葉が口をついて出るとき、私たちは多くの場合、“思考の自分”と“感覚の自分”の間で宙づりになっています。
「こうした方がいい」「この状況ではこう振る舞うべき」──そうした論理的な判断は、経験や常識、周囲の期待に支えられた“思考による自分”の判断です。
一方で、「なぜかわからないけどモヤモヤする」「その場にいたくなかった」──そうした非言語的な感覚は、言葉になる前の“感情や身体のレベルでの声”です。
本音とは、この“論理の顔”をした自分と、“感じているけど言語化されていない”自分のあいだに広がる、深い空白を見つめ直すことからしか立ち上がってこないものです。
多くの人が、本音を「はっきりしたもの」「言葉で説明できるもの」だと勘違いしています。
けれど、本音とは本来もっと“ぼやけたもの”なのです。
むしろ、いまの自分に言葉が追いついていない部分、つまりまだ言語化されていない感覚そのものが、本音の在処に近いのです。
たとえば、「やめたほうがいいとわかっているのに、なぜか続けてしまう」「好きか嫌いかも自分では判断がつかない」といった状態。
これらは本音がないわけではなく、思考と言葉によって正当化された自己像の奥に、本当の願いや痛みが隠れているだけです。
特に注意したいのは、「わかっているはずなのに納得できない」という感覚。
これは、自分の選択が思考には合致しているのに、感情的な実感がともなっていないときに生じやすい現象です。
つまり、頭と心が乖離しているのです。
私たちが“本音”にたどり着くには、思考の明晰さだけでなく、感情や身体の「違和感」に耳を澄ます時間が必要です。
それはすぐに答えが出るものではなく、むしろ「答えが出ない状態に耐えながら、その感覚を抱きしめ続ける力」によって、ようやく輪郭がにじみ出てくるようなものです。
本音とは、結論ではありません。
それは、今この瞬間の自分が、何に揺れていて、何を手放せずにいるのかを見つめるプロセスそのもの。
そしてそのプロセスこそが、自己理解の深化であり、未来への選択を“自分のもの”にする準備なのです。
第3章:身体が教えてくれる“まだ言葉にならない声”
「なぜだかわからないけど、気が重い」「理由はないけれど、不安」──
こうした状態は、私たちが言語で捉えきれない“何か”を、すでに身体が感じ取っている証です。
本来、身体は“今ここ”の環境に対して、最も繊細なセンサーです。
外の空気や音、人の気配、自分の内側のざわつきに至るまで、言葉になるよりも先に、身体はそれらを“感じている”のです。
しかし私たちは、思考で理解しようとするあまり、この身体感覚の“ささやき”を無視しがちです。
「そんなことを気にしていても仕方ない」
「感情に振り回されてはいけない」
そうやって、“言葉にできないもの”を無かったことにしてしまう──
それが本音の感覚を遠ざける、一番の要因かもしれません。
一方で、「胸が詰まる」「足が前に出ない」「妙に眠くなる」といった微細な反応に意識を向けることは、「まだ自分が理解していない何か」に気づく入口でもあります。
頭で「大丈夫」と思っていても、身体が緊張していたら、それは“どこかがNOと言っている”サインかもしれない。
言語では明確に説明できなくても、身体は常に「今の私」の状態を伝えてくれているのです。
だからこそ、自分の身体に“意識的に寄り添う”ことが大切になります。
たとえば、毎日の中で立ち止まり、「今、どんな感覚があるか?」を静かに観察するだけでも、
言葉になる前の違和感と、少しずつ対話できるようになっていきます。
“本音”とは、いつも鮮やかに言葉として現れるものではありません。
むしろ、身体が先に教えてくれる「まだ言葉にならない声」のなかにこそ、その兆しが宿っているのです。
次章では、その「兆し」をどう受けとめ、どう日常に活かしていくかを掘り下げていきます。
第4章:“違和感”と向き合う──自分を失わないための感覚の使い方
日常の中で、ふとした瞬間に湧き上がる“違和感”。
会話の最中、あるいは仕事の判断を下すとき、「なんかしっくりこない」「どこかズレている気がする」という微細な感覚──。
それは、単なる気のせいではなく、「本当の自分」からのシグナルかもしれません。
私たちは往々にして、その違和感をスルーします。
「気のせいだ」「空気を読まなければ」といった外的な基準によって、自分の感覚を押し込めてしまう。
けれどそれは、“他者の基準”で生きることに自ら身を委ねることでもあります。
“違和感”とは、今の自分と状況とのあいだにズレが生じていることを知らせるアラームです。
自分自身の軸が今どこにあるのか、何が満たされていて、何が欠けているのか。
そうした深層にアクセスするための、“感覚の入り口”なのです。
だからこそ、違和感に丁寧に向き合う習慣が、自分を失わずに生きるためには不可欠です。
決して大げさなことをする必要はありません。
「いま、なんとなく引っかかっていることは何か?」と、自分に静かに問いかけるだけでいいのです。
その違和感が何を伝えようとしているのか。
言葉にするにはまだ曖昧でも、その存在を否定せず、ただ受け取ってみる。
そうすることで、本来の自分との接続点が少しずつ輪郭を持ち始めるでしょう。
違和感は、不快なものではなく、むしろ自分を取り戻すためのコンパスなのです。
最終章では、その感覚をどう活かし、自分の生き方や選択に繋げていくかをまとめていきます。
まとめ:曖昧な自分を、急がずに抱えるという選択
私たちは「自分を理解したい」「本音を見極めたい」と願いながらも、その過程で多くの矛盾や曖昧さに直面します。
頭では整理できても、心が動かない。知識では納得しても、どこか満たされない。
そんな“ギャップ”に戸惑い、つい明確な答えを急ぎたくなる──。
けれど本当は、その曖昧さの中にしか見つからない「自分」がいるのではないでしょうか。
成長とは、わかりやすくなることではなく、むしろ「わからない自分」を抱えていく力を育てることかもしれません。
感情や身体の反応、“違和感”という名のささやかな声を信じ、
言葉になる前の微細な揺れに耳を傾ける──。
その積み重ねが、誰かの期待でも理想像でもない、“あなた自身”をつくっていくのです。
曖昧なままでも、進んでいい。
「まだわからない」と思える感性こそ、未来の変化に開かれている証拠なのだから。
だから今、どんな自分であれ、それを「未完成なまま抱えていく」という選択を、恐れずに持ってみてください。
言葉にならない“違和感”を、大切にしてみませんか?
頭ではわかっているのに、どこかスッキリしない。
そんな心の曖昧さや迷いも、あなたらしさの一部です。
私たちはその揺れに寄り添いながら、“次の一歩”を一緒に探していきます。