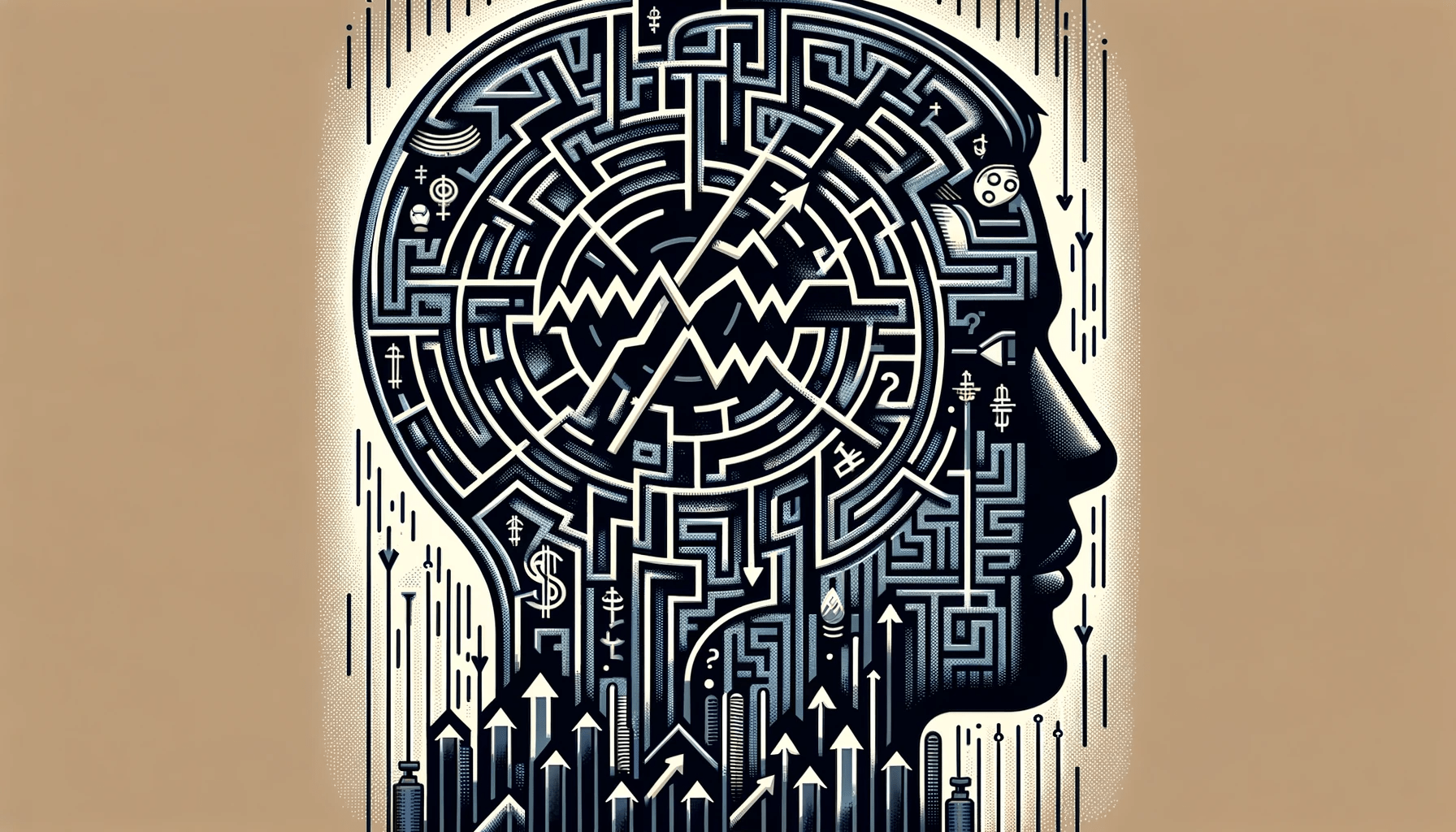
効用関数とリスク回避──合理的投資家モデルが「説明できること/できないこと」
投資理論の多くは「合理的な投資家」を仮定します。
合理的とは、手元の情報を(少なくとも統計的に)整合的に解釈し、期待効用を最大化するように選ぶ、という意味です。
この枠組みは、リスクとリターンの関係を整理するうえで強力です。
ところが現実の投資家は、情報の処理能力にも時間にも限界があり、さらに感情・記憶・焦り・安心といった“数式に入りにくい要素”の影響を受けます。
ここでは、効用関数が説明できることを丁寧に押さえたうえで、なぜそれだけでは足りなくなるのか、どこにズレが生まれるのかを、参照点(レファレンス・ポイント)と損失回避の視点から掘り下げます。
効用関数が説明できる「リスク回避」の骨格
効用関数の基本的な発想は、「お金の増減そのもの」ではなく「お金の増減がもたらす満足度(効用)」で人は判断する、という点にあります。
たとえば資産が増えるほど嬉しいのは確かでも、増え方が同じでも嬉しさは同じとは限りません。
資産が少ない人にとっての10万円と、資産が十分ある人にとっての10万円は、心理的な重みが違う。
この直感を数式にすると、一般に効用関数は右上がりで、かつ次第に寝ていく形(限界効用の減少)になります。
こうした形は、同じ期待値なら“振れ幅が小さいほう”を好む、というリスク回避の行動を自然に導きます。
たとえば「確実に3万円得る」か「50%で6万円、50%で0円」を比べたとき、期待値は同じでも前者を選びやすい、という現象です。
合理モデルの良さは、ここにあります。
リスクを避けるのは臆病だからではなく、満足度の曲線の形から整合的に導かれる。
さらにこの枠組みは、リスクプレミアム(不確実性を引き受ける対価)という考えにもつながり、資産価格や期待リターンを論理的に扱える土台を与えます。
ただし、この時点では「損失の痛みが利得の喜びより大きい」という非対称性は、必ずしも中心に置かれていません。
そこが次の論点になります。
合理モデルの限界は「最適化」より先に「認識」に出る
合理モデルが現実からズレるとき、多くの人は「最適化ができていない」と言いがちです。
しかし実際には、最適化以前に“入力”が歪みます。
入力とは、情報の取り込み方、つまり「何を重要とみなし、何を無視するか」です。
市場ではニュースが絶えず流れ、指標も多岐にわたり、SNSや掲示板の声も混ざります。
理論上は、すべての情報を同じ重みで吟味するのが理想に見えますが、現実には時間も集中力も足りません。
結果として、人は情報をフィルタリングし、分かりやすい指標、印象の強い出来事、直近の経験、他人の確信に引きずられます。
ここで起きるのが、アンカリング(最初に見た数字が基準になる)、代表性(それっぽい物語に乗る)、確証バイアス(見たい情報だけ集める)といった偏りです。
さらに、含み損益がリアルタイムで見える環境は、判断の頻度を増やし、短期のノイズに反応させます。
合理モデルが想定するのは「落ち着いて効用を比較する投資家」ですが、現実は「刺激の多い環境で、断片をつなぎ合わせて意思決定する投資家」です。
この差が、理論と行動のギャップを生みます。
つまり、非合理は“性格の問題”というより、情報環境と時間制約が作る“構造の問題”として理解したほうが、対策が立ちます。
参照点(購入価格)がつくる「感情の地形」
投資家の心理を理解するうえで鍵になるのが、参照点(レファレンス・ポイント)です。
典型例は購入価格で、ここが「勝っている/負けている」を判定する境界線になります。
たとえば購入価格が1,000円の株が、995円、1,005円と小さく揺れるだけで、感情は大きく揺れます。
数字としては±0.5%にすぎなくても、「含み益か含み損か」というラベルが付いた瞬間に、重みが変わるからです。
ここでは、合理モデルの“絶対値としての資産”よりも、“変化としての差分”が支配的になります。
さらに興味深いのは、利得局面と損失局面で感受性が一定ではないことです。
上昇が始まったばかりの小さな含み益は、驚くほど甘美に感じられます。
しかし含み益が積み上がるにつれて、同じ増加幅でも喜びは薄れがちです(利得側の限界感応の低下)。
逆に下落局面では、最初の小さな含み損が強い不安を生み、さらに損失が膨らむと、ある種の麻痺が起きやすい(損失側の感応の変化)。
この“地形”が、損切りを遅らせたり、利確を早めたりする行動として表に出ます。
購入価格は単なる数字ではなく、感情の座標軸になってしまう。
ここを理解しないと、理論上は正しいはずの判断が、実行段階で崩れます。
利益のときに守り、損失のときに攻める──リスク態度の反転
多くの投資家は、含み益の局面ではリスクを避け、含み損の局面ではリスクを取りがちです。
合理モデルの直感だけで見ると不思議ですが、参照点を中心に据えると筋が通ります。
含み益は「守りたいもの」になり、わずかな下落でも“得たものが失われる”と感じられて不快になるため、早めに確定したくなる。
一方、含み損は「取り返したいもの」になり、リスクを取ってでも元に戻したいという衝動を生みます。
この反転は、プロスペクト理論が強調するポイントです。
利得と損失を対称に扱わず、損失の側をより重く評価する(損失回避)という非対称性が、行動の方向を変えます。
さらに、損失を確定すると“失敗が確定する”という心理的痛みも加わり、判断は数字の比較から、自己評価の防衛へと移ります。
すると、期待値が悪化してもポジションを抱え続け、反対に期待値がまだ良好でも利益を確定してしまう、といった現象が起こります。
ここで重要なのは、投資家本人が「合理的に判断しているつもり」でいる点です。
だからこそ、後から振り返ると説明が難しくなる。
しかし、参照点と損失回避を導入すると、行動の一貫性はむしろ増します。
問題は“理屈がない”ことではなく、“理屈が別の層(感情の地形)にある”ことです。
複数銘柄になると「評価」はさらにねじれる
単一銘柄なら、参照点は比較的単純です。
しかし複数銘柄を持つと、評価は急に複雑になります。
たとえばAで大きな含み益、Bで含み損という状態のとき、人は「全体でプラスだから大丈夫」と感じやすい。
この安心感は、実務的には一見健全に見えますが、同時に“損失銘柄への対処を遅らせる”方向へ働きます。
逆に、全体がわずかにマイナスだと、含み益の銘柄を急いで利確して“気分を良くしたい”衝動が出て、損失銘柄だけが残りやすい。
こうした偏りは、合理モデルの枠内では「全体最適(ポートフォリオの期待効用)」として統合されるはずですが、現実の心理は必ずしも統合しません。
人はしばしば、銘柄ごとに“別会計”で感じます(メンタル・アカウンティング)。
その結果、ポートフォリオ全体のリスクを下げるべきタイミングで、逆にリスクが残る構造へ移行することがあります。
さらに、評価が難しい損失銘柄ほど情報を見たくなくなり、モニタリングが弱まる。
情報過多と時間制約がここでも再び効いて、判断は“面倒なものを後回しにする”という人間らしい方向に傾きます。
理論を学ぶほど、むしろこのねじれを早期に発見し、仕組みで補う必要があります。
実務への落とし込み──非合理を前提に「手順」で支える
合理モデルと行動ファイナンスの議論は、知識として面白いだけでは意味がありません。
大事なのは、意思決定が歪むポイントが分かったなら、そこに手順を置くことです。
たとえば、参照点に引きずられやすいなら「購入価格だけで判断しない」ではなく、「判断に使う基準を事前に固定する」。
含み損でリスクを取りやすいなら「冷静になろう」ではなく、「損失が一定幅に達したら機械的に縮小する」など、感情より先に動くルールを用意する。
情報過多が問題なら「良質な情報だけ見る」ではなく、「追う指標と頻度を限定する」。
複数銘柄のねじれが起きるなら「全体で見よう」ではなく、「銘柄別の撤退条件と、全体のリスク上限を分けて管理する」。
こうした設計は、勝率を上げる魔法ではありませんが、少なくとも“崩れ方”を小さくします。
投資の失敗は、理論を知らないことより、分かっているのに実行できないところで起きます。
だからこそ、非合理を否定せず、前提として受け入れ、そのうえで手順に落とし込む。
理論は地図であり、現場を歩くのは自分です。
歩き方を支えるのは、気合よりも、あらかじめ決めた小さな手順です。



