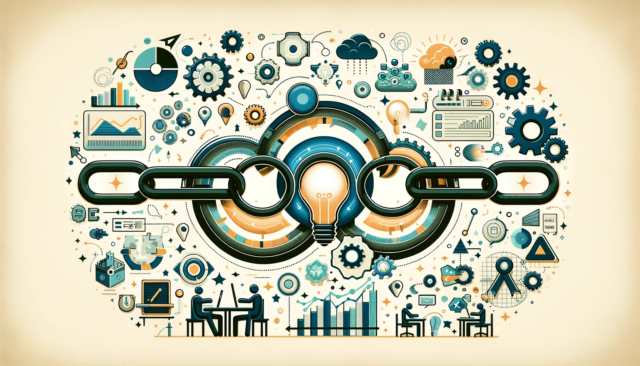
常に論理で固めるのは窮屈でも、組織・顧客・審査・会議など特定の局面では論理欠如が即不利益になる。だから使い分ける。
使い分けの原則
- 合意形成・稟議・レビュー:再現可能性を最優先(データ→解釈→決定)。
- 発想・探索・ブレスト:直観を先行→後追いで最小の論拠を添付。
- 対外説明:事実→影響→代替→要請の順で簡潔に。
論理の破綻に“先に”気づく技法
言語は不完全。だから破綻検出が核心になる。
逆順チェック(結論→根拠→前提)
- 結論:何を主張?(一文)
- 根拠:数値・事例・一次資料(出所と取得日)
- 前提:対象・期間・定義・環境(暗黙条件を可視化)
典型的な欠落
- 時間前提の古さ/対象のズレ/用語定義のブレ
因果とMECEで“論点を痩せさせる”
因果形式の把握
- X→Y:単純因果(例:値上げ→CVR低下)
- X×Z→Y:交互作用(例:新規のみCVR低下、既存は無影響)
- Y→X:逆因果の見落とし(例:需要減→値上げに見える)
MECE(漏れダブり)チェック
- 分解軸は1本(顧客タイプ“だけ”で切る → 2段で止める)
- 「その他」が30%超で再分解、20%以下を目安に。
定義・リサーチの“運用ルール”
用語の先出し
【定義】継続率 = 30日後再利用率(分母:初回利用者、期間:2025/1–3)
一次→二次の順
- 一次:ログ/台帳/原票/契約書
- 二次:調査レポート/記事/要約
検証メモ(最短)
出所/取得日/N数/集計方法/反例の有無/次回更新日
演繹と帰納の切替え
演繹(トップダウン)
方針説明・稟議に最適。前提→規則→結論を1スライドで。
帰納(ボトムアップ)
探索段階に最適。観察→パターン→仮説→実験→学習。
会話テンプレ(1分)
- 主張(一文)→根拠(3点以内)→反論先回り→要請(相手の次アクション)
クリティカル思考:運用チェックリスト
因果チェック
- 原因候補は観測可能か(測れないものは補助要因に降格)
- 交互作用を1つだけ入れて比較(例:新規/既存)
- 逆因果を反証(時系列・先行指標)
MECEチェック
- 分解軸1本・2段止め・その他≤20%
バイアス&ロジックエラー早見
よくある認知バイアス
- 確証バイアス:好都合な証拠だけ拾う → 反例を先に3件集める
- 生存者バイアス:成功例だけ見る → 失敗母集団の条件を見る
- アンカリング:初期数値に固着 → 別出所の独立推定を置く
- 権威バイアス:肩書きに引っ張られる → 一次データ優先
論理エラー
- 早計な一般化:Nが少ないのに結論 → 最低限の検出力を確認
- 偽の因果:相関=因果の誤認 → 介入の前後比較を置く
- 循環論法:結論を前提に含める → 定義と主張を切り分け
即使用テンプレート集
① CRP(結論・根拠・前提)
【結論】_____。
【根拠】1) _____(出所:____/取得:____)
2) _____
3) _____
【前提】対象:____/期間:____/定義:____
【反論と対応】想定反論:____/対策:____
【要請】相手にしてほしいこと:____(期限:____)
【根拠】1) _____(出所:____/取得:____)
2) _____
3) _____
【前提】対象:____/期間:____/定義:____
【反論と対応】想定反論:____/対策:____
【要請】相手にしてほしいこと:____(期限:____)
② 逆順レビュー(結論→根拠→前提)
[1] 結論(一文):
[2] 根拠(最大3):
[3] 前提(対象/期間/定義):
[4] 欠落(時間・対象・定義):
[5] 反例(最低1つ):
[2] 根拠(最大3):
[3] 前提(対象/期間/定義):
[4] 欠落(時間・対象・定義):
[5] 反例(最低1つ):
③ 因果・MECEミニシート
因果形式: □単純 □交互作用(Z=____) □逆因果検証済
分解軸:____(2段まで)/その他:____%
測定:指標____/集計____/更新日____
分解軸:____(2段まで)/その他:____%
測定:指標____/集計____/更新日____
④ 用語レジストリ(1行定義)
用語/定義/算出式/分母分子/対象域/バージョン/最終更新
⑤ 会議アジェンダ(15分版)
0–3分:結論(1文)と期待アウトカム
3–8分:根拠(最大3)+反例
8–12分:代替案×2(メリデメ)
12–15分:要請・期限・責任者(RACI)
3–8分:根拠(最大3)+反例
8–12分:代替案×2(メリデメ)
12–15分:要請・期限・責任者(RACI)
拡張事例:広告費よりも“継続率”が効いていた
Before(ありがち)
- 売上低下=広告費が足りない、の単因果仮説
- 外部事例の横滑り(対象・定義が不一致)
After(再定義と検証)
- MECE分解:流入→転換→継続
- 交互作用:新規はCVR低下、既存は30日継続率の低下
- 実験:LPのファーストビュー差し替え、オンボーディング改善
- 結果:新規CVR+12%、30日継続率+8pt → 売上回復。広告増額は二次手段へ降格
7日間ブートキャンプ(現場運用)
Day1:用語レジストリ
主要KPIを1行定義。分母分子・期間を固定。
Day2:逆順レビュー
直近の重要主張をCRPで1枚化。
Day3:因果仮説を3本
単純/交互作用/逆因果の3型を用意。
Day4:MECE分解(2段)
その他20%以下まで分解。
Day5:データ取得動線
一次→二次の順に取得計画。
Day6:反例探索
反証3件を先に集める。
Day7:15分レビュー
会議テンプレで意思決定→RACI確定。
意思決定フレーム:評価軸を事前に固定
多基準評価(MCDM)ミニ
軸:効果 / コスト / リスク / 実装速度 / ブランド整合
重み:0.35 / 0.2 / 0.15 / 0.2 / 0.1(合計=1)
案A:__点 案B:__点 案C:__点 → 採用:__
重み:0.35 / 0.2 / 0.15 / 0.2 / 0.1(合計=1)
案A:__点 案B:__点 案C:__点 → 採用:__
注意
- 重みを事前に合意(後出し調整はNG)
- 定性的軸もラベル化(High/Med/Low→数値化)
データの鮮度・信頼度の扱い
鮮度ポリシー
- 運用KPI:週次更新/意思決定は最新週のみ使用
- 市場データ:四半期更新/前年同週比較を併記
エビデンス階層(簡易)
- Level1:自社一次データ(追試可能)
- Level2:公的統計・査読
- Level3:業界レポート
- Level4:記事・ブログ(参考)
よくある失敗と回避策
失敗
- 会議で定義がない
- 「その他」依存の分解
- 反例ゼロで前のめり
回避
- 冒頭60秒で定義・期間・対象を読み上げ
- 分解は2段止め/その他≤20%
- 反例3件を先に用意(確証バイアス対策)
まとめ:論理は“常時ON”ではなく“状況で最大化”
前提・因果・定義・MECEを押さえ、結論→根拠→前提の逆順で破綻検出。探索では直観、意思決定で論理を最大化する——この切替え運用が最短で成果に繋がる。



