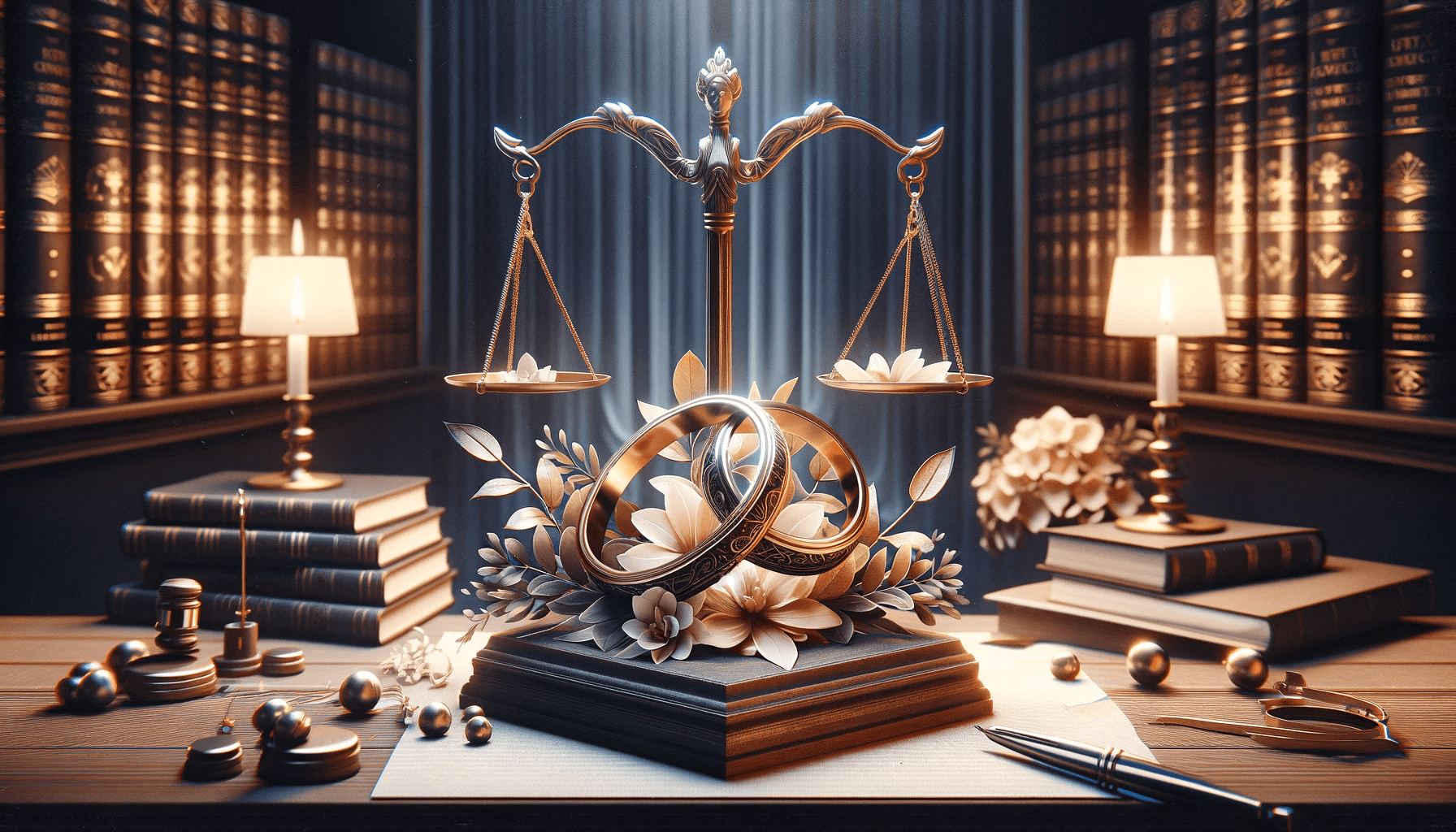
婚とは、法的な契約であると同時に、心と生活の約束でもあります。
お互いを尊重し、支え合いながら生きていく──この暗黙の契約が崩れたとき、夫婦関係は静かに揺らぎ始めます。
本稿では、その中心にある「扶助義務」を切り口に、現代の夫婦関係と離婚に至る心理的・社会的構造を考えます。
夫婦をつなぐ「扶助義務」とは何か
法律上、夫婦には「互いに協力し扶助する義務」が定められています。
これは単なる生活費の分担や家事の手伝いではなく、相手の心身の安定を支える責任を意味します。
つまり、金銭面・精神面・生活面すべてにおいて「共に生きる意志の共有」が求められるのです。
しかし現実には、この義務が形骸化しやすい側面もあります。
例えば、配偶者が毎晩のように飲み歩き、家事や育児を一方に任せきりにしてしまう。
それが慢性的に続くと、やがて「支え合い」ではなく「支配と放棄」の構図に変わっていきます。
私自身の経験から見えること
私にも、過去に同じような時期がありました。
毎晩のように遅くまで飲み歩き、帰れば妻が静かに食事を温めて待っている。
それでも彼女は一度も文句を言わず、ただ受け入れてくれた──その寛大さが、私たちの関係を支える力になっていたのです。
ただし、これは例外的なケースです。
多くの夫婦では、このような不均衡が長く続くと、関係の疲弊とすれ違いが深まります。
継続できた背景には、問題が起きたときに立ち止まり、互いの役割や距離を見直す習慣があったからだと、今になって感じます。
変化する“役割”と、新しい支え合いのかたち
現代では、「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という固定的な役割観が崩れつつあります。
共働き世帯が増え、家庭内での役割も柔軟さが求められるようになりました。
大切なのは、どちらが何をするかではなく、相手が抱える負担や心の状態を理解し合う姿勢です。
夫婦関係は「分担」よりも「循環」に近い構造を持っています。
一方が疲れたとき、もう一方が支える──そしてまた、逆の立場になる。
この循環が失われるとき、関係は硬直化し、離婚という選択が現実味を帯びてくるのです。
関係を再構築するための3つの視点
- 対話をやめないこと: 感情的な衝突を避けるために沈黙を選ぶと、誤解は固定化します。小さな会話を絶やさないことが大切です。
- 期待を“更新”すること: 結婚当初の理想像に囚われず、現実の変化に合わせて関係性を再定義すること。
- 助けを求める勇気: 夫婦だけで解決できない問題もあります。カウンセリングなど外部の支援を活用することは、弱さではなく成熟の証です。
扶助義務とは、単なる義務ではなく「支え合う選択を続ける自由」でもあります。
その自由を維持するためには、日々の小さな軌道修正が欠かせません。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の法的助言を行うものではありません。
離婚や夫婦関係に関する具体的な法的問題については、必ず専門家へご相談ください。
問題を整理し、互いの立場を見直すことで、関係は変わっていきます。
感情と現実の間に、もう一度「協力」の輪郭を描き直しましょう。



