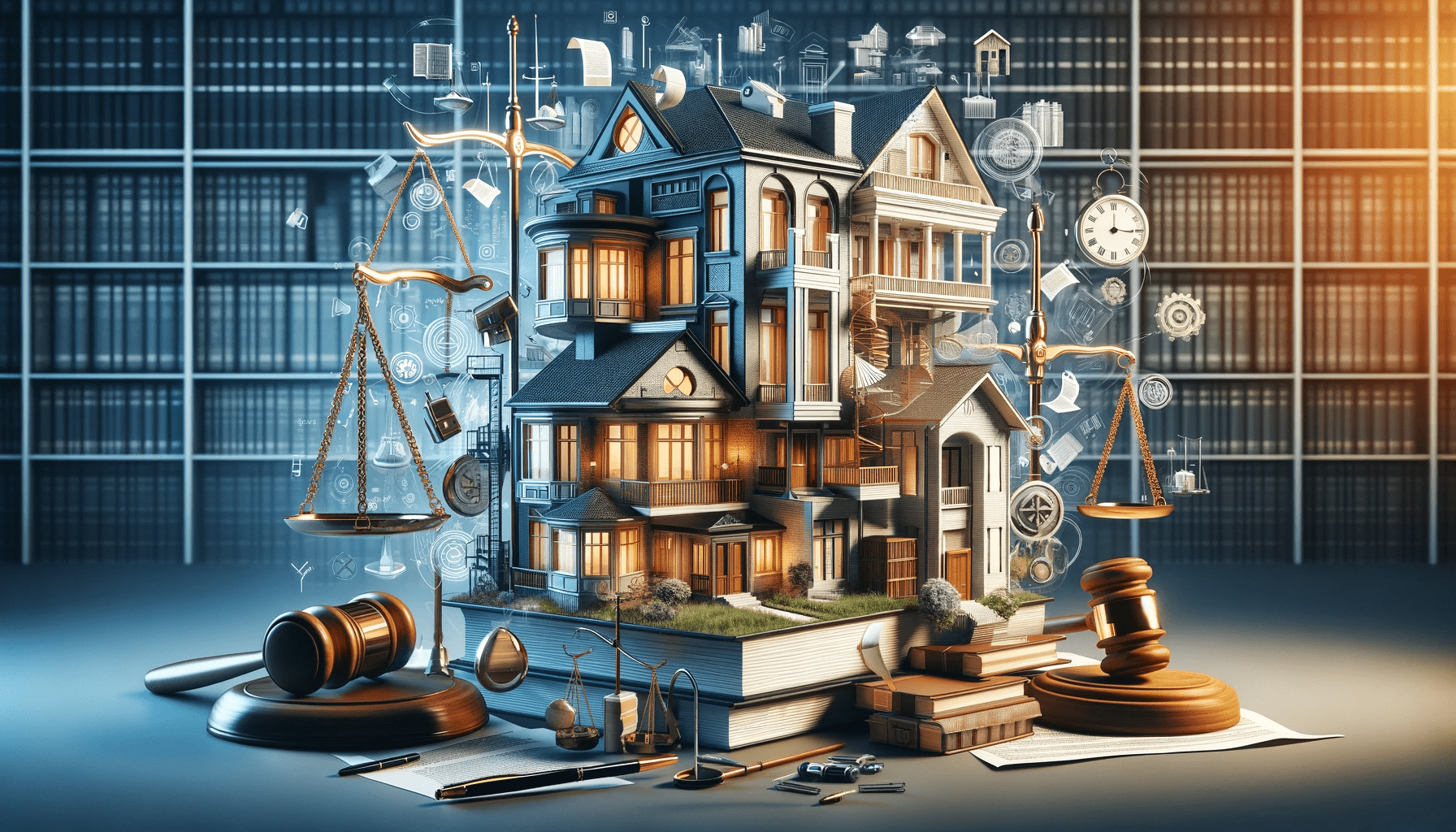
民法の規定
不動産に関する規制は、実際には非常に広範な範囲にわたります。公法上の規制は、国や自治体が公共の利益を保護するために設けられています。一方、私法上の規定は、個人や企業間の取引を円滑に進め、争いを防ぐためのものです。以下、これらの規制を簡単に解説します。
- 公法上の規制:
- 都市計画法: 都市の計画的な発展と管理を目的とし、建築物の高さや容積率、用途地域などを規定しています。
- 建築基準法: 建物の構造や設備、安全基準などを定めています。
- 農地法: 首都圏等での農地の転用を制限し、食料自給率の確保や農業の維持を図る目的で制定されました。
- 土地利用法: 特定の地域での土地の利用を制限することで、環境の保護や景観の維持を目的としています。
- 私法上の規定:
- 民法: 民法は、財産権の基本的な概念や、契約、物権、相続などの私的な関係を規定しています。不動産取引においては、土地の売買契約や賃貸契約、隣地の権利関係などが該当します。
- 不動産登記法: 土地や建物の所有者、担保権、その他の権利関係を公示するための制度を定めています。登記を通じて、第三者に対して権利を確保することができます。
- 宅地建物取引業法: 宅地建物取引の公正を確保し、消費者の利益を守るための規制や取引業者の資格に関する事項を規定しています。
まとめると、不動産に関する規制は、公共の利益と個人間の安全な取引の両方を保護する目的で設けられています。これらの規制は、不動産取引におけるトラブルを防ぐための重要な役割を果たしています。
不動産取引における民法の補充規定について
不動産取引において特に重要なのは補充規定です。
これは、当事者間で契約や取引の詳細について特段の約束をしていない場合に適用される規定です。
以下は、不動産取引に関連して日本の民法で特に重要な補充規定や関連する規定をいくつか挙げてみます:
- 物の売買に関する規定(民法第555条以降):
- 購入者は、契約の履行を求めることができます。
- 売買の対象となる物(不動産)は、契約時点での状態を保持している必要があります。
- 売主は、物件の所有権を移転する義務があります。
- 欠陥担保責任(民法第562条以降):
- 不動産に潜在的な欠陥があった場合、売主は購入者に対して責任を持つことが規定されています。
- 売主が欠陥を知っていて教えなかった、または過失によって知らなかった場合、購入者は契約の解除や減額を求めることができます。
- 重要事項の告知義務:
- 不動産取引において、売主や仲介業者は、物件に関する重要事項を購入希望者に告知する義務があります。これに違反した場合、購入者は契約の無効や損害賠償を求めることができます。
- 物権移転の登記:
- 不動産の所有権の移転は、登記を行うことで第三者に対して効力を持ちます。登記をしない場合、第三者の権利を優越させる危険があります。
- 担保権(抵当権):
- 不動産を担保として借金の返済を保証する場合、抵当権の設定が行われます。これに関する詳細も民法に規定されています。
これらの補充規定や関連する規定は、不動産取引におけるトラブルを防ぐためのものであり、取引の安全性と信頼性を保障するためのものです。不動産取引に関与する際は、これらの規定を十分に理解しておくことが重要です。
①法律行為などと法律効果
図表5-1
| 法律行為など | 法律効果 |
契約
|
|
b)不法行為
|
|
c)時効取得
|
|
d)財産分与
|
|
e)相続
|
|
②法律行為に間違い(瑕疵)があった場合
a)AのBに対する意思表示(例:売ります、あげます)に瑕疵が存した場合
- ア)強迫によりなされた場合 → 取り消しうる(民法96条)
- イ)詐欺によりなされた場合 → 取り消しうる(民法96条)
- ウ)錯誤によりなされた場合 → 無効(民法95条)
- 工)虚偽の表示によりなされた場合 → 無効(民法94条)ただし、以上のうち一定の場合に善意の第二者が保護される(民法96条3項、94条2項)。
b)AまたはBに本来備わるべき資格・能力が存しない場合
- ア)未成年者(法定代理人の同意なし)→ 取り消しうる(民法5条)
- イ)被補助人(補助人の同意なし)→ 取り消しうる(民法17条)
- ウ)被保佐人注4(保佐人の同意なし)→ 取り消しうる(民法13条)
- 工)成年被後見人注5 → 取り消しうる(民法9条)
- オ)無権代理人(代理人と称するが代理人ではない)→ 本人に効力が及ばない(民法113条)
- 力)他人(本人と称するが本人でない)一 本人に効力が及ばない
ただし、以上のうち一定の場合に善意の第二者が保護される(民法109条~112条)
保証:抵当権設定金銭消費貸借契約のケーススタディー
主たる債務者Aが、債権者Bへの債務の履行をしない場合に、債務者Aに代わりAの債務を履行をしなければならないこととなる保証人Cの義務を保証債務といいます。
また、保証関係のうち、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する形態を連帯保証といい、通常の保証よりも債権者に有利な点注6が多いため、通常の保証よりも実務では頻繁に用いられます。
次回は、「資産流動化法の概要などを知って、不動産の投資分析に役立てる」です。
ではまた。




