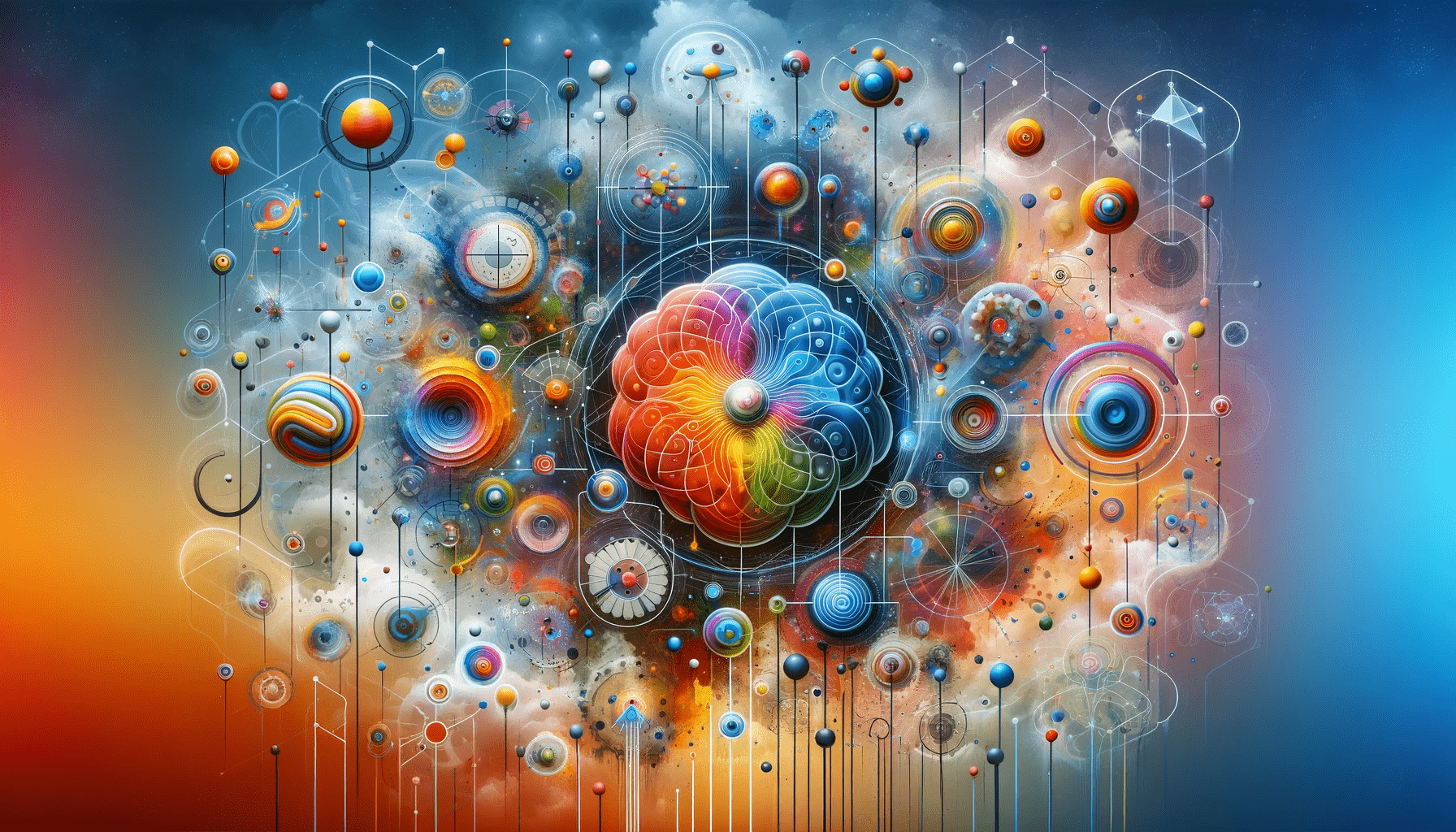
類似性×思考プロセス──“似て非なる”を見抜き、使いこなす
「これは前にも見た」「あの時と似ている」──人の思考は、類似性(Similarity)を足がかりに動きます。類似性は学習・記憶・推論の入口であり、思考プロセス(認識→理解→記憶→推論→判断)を駆動する燃料でもあります。ただし、表面だけの“似ている”に流されると、誤判断や安易な一般化に直行します。本稿は、科学的根拠で土台を固めつつ、実務で使えるテンプレに落とすガイドです。
1. 科学的な土台(ごく簡潔に)
- カテゴリー化は“家族的類似”で起きる:人は原型(プロトタイプ)や特徴の重なりで素早く分類する[1]。
- アナロジーは“構造”の写像:表面の似姿ではなく、関係のパターン対応で新課題に転用する[2]。
- 思考は前頭葉ネットワークの協調で進む:発想やマインド・ワンダリングも含め、文脈に応じてダイナミックに切替わる[3]。
- 記憶は“似た表現の近さ”で呼び出される:頭の中でも、類似度(近さ)が検索効率を左右する(表現類似・想起)[4–5]。
要するに──表面の似姿に頼ると誤る。構造(関係・制約・因果)の類似を掴めれば、転用と創造が進む。
2. 現場で効く「類似性の使い方」テンプレ(コピペOK)
2-1. 構造写像メモ(Gentnerの着想を実務化)
【Source(既知の事例)】何がどううまくいった/失敗した? 【Target(今回の課題)】何を達成したい? 【構造の対応】要素A↔A'、関係R↔R'、制約C↔C' 【相違点】今回は何が違う?(環境/規模/制約/利害) 【転用ルール】何を残し、何を捨て、何を追加する? 【最小実験】5分 or 小口で試せる一手は? いつ測る?
2-2. プロトタイプの落とし穴チェック
【原型】自分の頭の“典型像”は何か? 【例外】原型に当てはまらない実例を3つ挙げよ 【境界】そのカテゴリーの“入/出”の基準は明文化できるか? 【誤警報】表面類似に釣られてないか?(色/語感/ラベル)
2-3. 思考プロセスの配線表(認識→理解→記憶→推論→判断)
【認識】入力を分解(数値・制約・利害・時系列) 【理解】因果/関係/制約を書き出す(図でも可) 【記憶】似た事例を3件検索(成功/失敗/反例) 【推論】構造写像で転用案を2つ 【判断】転用案→最小実験→測定指標→期日
3. “似て非なる”を見抜く:よくある誤作動と修正(事例つき)
表面類似の罠:用語・見た目が近いだけ
修正:「関係・制約・目的」を3行で対比。1つでもズレが大きければ別物。
- 事例A|採用:前職「プロダクトマネージャー」=現職PMと同じだと思い採用→実は前職は営業主導の提案窓口。
対比:関係=意思決定権の所在/制約=開発リソースの配分ルール/目的=売上KPIか顧客満足か。 - 事例B|投資:チャート形状が似ているからと強気にIN→金利局面が真逆。
対比:関係=金利×需給×バリュエーション/制約=レバ規制・税制/目的=短期トレードか長期保有か。 - 事例C|学習:「データ基盤」と「BI(ビジネス・インテリジェンス)ツール」を同一視→要件定義が崩壊。
対比:関係=データ生成→蓄積→変換→可視化の連鎖/制約=スキーマ・レイテンシ/目的=意思決定の速度か正確性か。
近似での過一般化:一つの成功事例を普遍化
修正:先に反例3つ→適用条件を明文化。
- 事例D|プロダクト:A社で値上げ成功→全顧客に一律適用し離反発生。
反例3つ:価格弾力性が低い業界/代替多い市場/サブスクの解約摩擦が小さい設計。
適用条件:独自価値の明確性、競合構造、切替コスト。 - 事例E|働き方:「朝活が最高」で全員に義務化→夜型の生産性が激減。
反例:時差協業/夜間保守/クリエイティブ作業。
適用条件:同期/非同期の比率、顧客稼働時間、成果の測定法。
確証バイアス:好きな類似だけ拾う
修正:「もし逆なら?」の反事実を先に1行。
- 事例F|マーケ:自社は“コミュニティ起点が合うはず”→エンゲージは高いがLTV伸びず。
反事実:もしSEO起点の方がCACが低いなら?→試算してみる→集客ミックスを再設計。 - 事例G|投資:好きなテーマETFに有利な指標だけ引用。
反事実:もし金利と資金フローが逆風なら?→サイズ半減+エントリ延期。
過去への呪縛:古い原型に固執
修正:直近12か月の新データでプロトタイプ更新。
- 事例H|営業:昔は大口は対面必須→今はオンライン決裁比率が上昇。
アップデート:直近12か月の受注経路データで原型を再定義(対面=高額条件下のみ等)。 - 事例I|採用:「名門大卒=即戦力」原型に固執→実務スキル不一致。
アップデート:過去12か月のオンボーディング速度・定着率で原型を再学習(課題分解力やチーム適合を重視)。
ポケットチェック(会議前30秒)
① 関係・制約・目的の3行対比を作ったか? ② 反例を3つ挙げたか?(過一般化の防止) ③ 「もし逆なら?」の反事実を書いたか? ④ プロトタイプを直近12か月のデータで更新したか?
4. 学習・仕事・投資の3シーン例
学習
新分野を覚えるときは「対比セット」(似てるが決定的に違う2つ)で覚える。例:分類AとBの決定境界だけにマーカー。
仕事
過去の提案書をソースに、今回の顧客要件(Target)へ構造写像。必ず“相違点”を先に書くことで使い回しの事故を防ぐ。
投資
似た市況を探すとき、表面のチャート形状ではなく、金利・需給・政策・バリュエーションの関係で比較。1要素一致は「似てない」と判断。
5. 7日プロトコル:類似性の“衛生管理”を身につける
- Day0:プロトタイプの棚卸し(自分の“典型像”を書き出す)。
- Day1–5:毎日1テーマに構造写像メモ+反例3つ。
- Day6:1週間で最も効いた写像ルールを行動ルールへ昇格。
【今週の写像ルール】(例)「目的→制約→関係の順で対応付ける」 【来週の最小実験】(例)会議前に“相違点”3行を必ず書く
6. まとめ──“似ている”は入口、“構造”が本体
類似性は思考を加速させますが、使い方を誤ると暴走します。表面ではなく構造を写像し、最小実験で検証する。これだけで、学び・仕事・投資の精度は目に見えて上がります。
[1] Rosch, E., & Mervis, C. B. (1975). Family resemblances… Cognitive Psychology, 7(4), 573–605.
[2] Gentner, D. (1983). Structure-mapping… Cognitive Science, 7(2), 155–170.
[3] Christoff, K., et al. (2016). Mind-wandering as spontaneous thought… Nature Reviews Neuroscience, 17(11), 718–731.
[4] Kriegeskorte, N., et al. (2008). Representational similarity analysis… Frontiers in Systems Neuroscience.
[5] Nosofsky, R. M. (1986). Attention, similarity, and the identification–categorization relationship. JEP: General.



