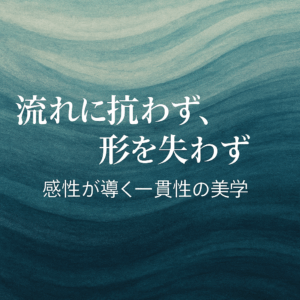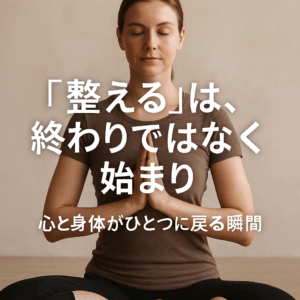クマは、人里に降りてきたのではなく、人間を“恐れなくなった”。
この視点に立つと、事態の輪郭がまったく違って見えてきます。
自然は、人間をどう感じ取っているのか
動物は、相手の動きや姿勢、声、匂いといった情報を瞬時に統合し、“脅威かどうか”を判断します。
クマもまた、音や匂いを通して、人間という存在の輪郭を記憶し、学習してきました。
かつての山村では、発砲音や焚き火の煙、人の声や足音が日常的にありました。
それらはクマにとって、「ここには支配的な存在がいる」という明確なサインでした。
けれど今はどうでしょう。人の生活音は消え、夜でも光がなく、匂いも希薄です。
自然の側から見れば、そこはもはや“人の空間”には見えないのかもしれません。
クマは、ただ食料を求めて里へ降りてきたのではなく、「危険の信号が消えた場所」へと自然に足を運んでいるのです。
そして人間は、そのことに気づかぬまま、「なぜ被害が増えるのか」と首をかしげている。
“恐れられない存在”になりつつある人間
最近の事例の中には、畑仕事中の高齢者や、一人で山道を歩く女性が襲われたケースが多く見られます。
その姿は、威圧的でも、敵対的でもありません。
穏やかで、静かで、動きがゆっくりしている。
それは人間にとっては優しさや平穏の象徴ですが、クマにとっては“危険を感じない存在”として映る可能性があります。
クマは、見た目や体格だけでなく、声の高さ、歩くリズム、体の重心、匂いの微妙な違いまで識別します。
そして、過去に危害を与えなかった人々の特徴を記憶する。
つまり、クマは「人間そのもの」ではなく、「自分に害を与えるかどうか」で相手を分類しているのです。
この構図を反転して見れば、人間の存在感が自然の中で薄れつつあるということでもあります。
“恐れられない”というのは、支配ではなく、認識されていないということ。
それは文明の進歩ではなく、関係の希薄化の兆しかもしれません。
境界を失った世界で、何を再建すべきか
人間と自然の関係は、いま“境界を失った状態”にあります。
恐怖を与えることで線を引くのではなく、存在の強度そのものを失っている。
クマの出没は、その“曖昧な輪郭”を鏡のように映し出しているとも言えるでしょう。
自然は、音・光・匂いといった「知覚の痕跡」で世界を理解します。
だからこそ、私たちは「排除」ではなく「再認識」というかたちで境界を築く必要があります。
静けさを守りながらも、存在を知らせる。
近づかれないようにするのではなく、“そこに人が生きている”ことを知らせる。
それが、恐怖でも優しさでもない、関係のデザインです。
自然と向き合うとは、自然に恐れられることでも、愛されることでもない。
「互いに理解される距離」をもう一度設計し直すことなのだと思います。
見られている、という感覚を取り戻す
クマの襲撃を単なる事件として捉えるのではなく、
自然が人間を観察し、学び、適応しているという視点から見つめ直すと、
それは“自然の知性”との再接続の問題でもあります。
私たちは長い間、「自然を観察する側」であり続けました。
しかし今、観察される側に立たされている。
そのことに、どれほどの謙虚さを持って気づけるか――それがこの時代の倫理です。
自然は、人間を恐れなくなったのではなく、人間を「感じなくなった」のかもしれません。
そして、感じ取られなくなった人間は、やがて自然の中で“風景の一部”へと溶けていく。
その静かな予兆に、私たちはどこまで耳を澄ませられるでしょうか。