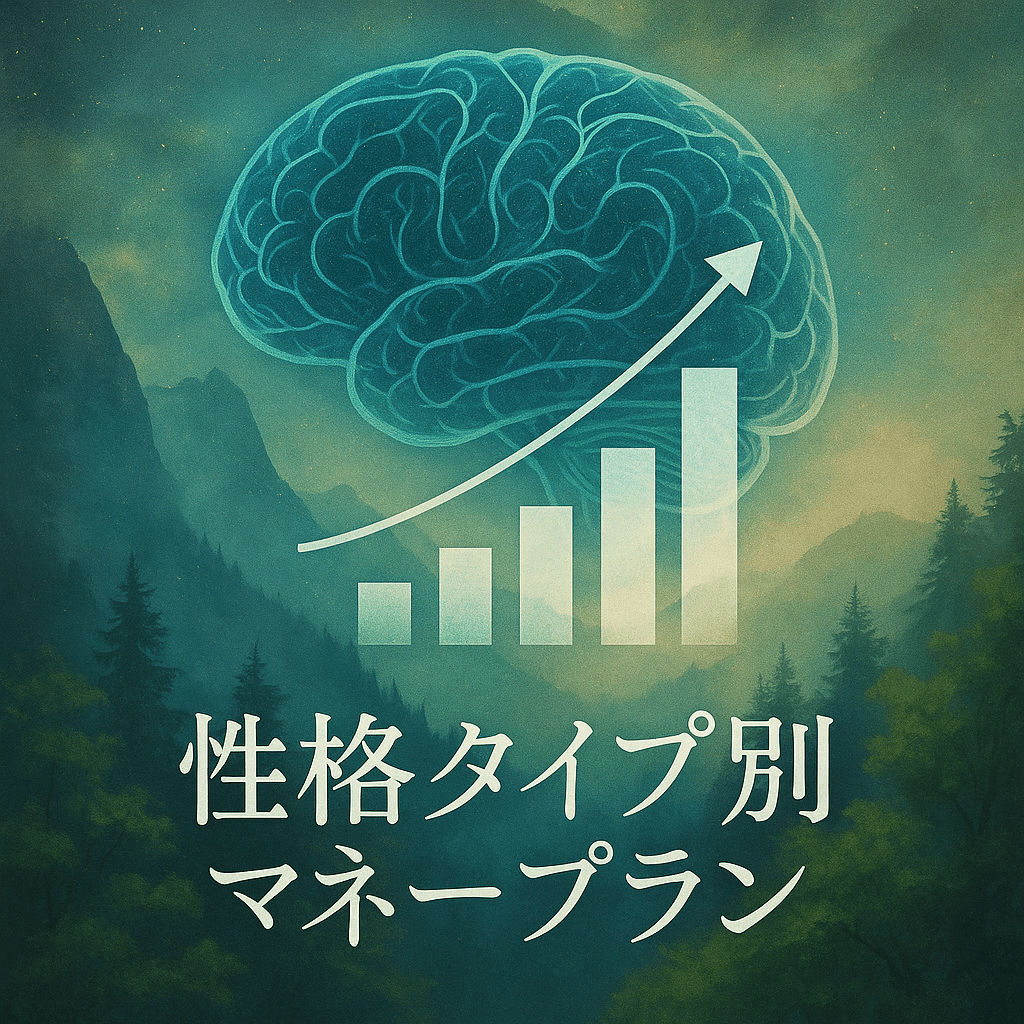
ユングのタイプ論とは
アーユルベーダ体質(ドーシャ)を3分でセルフチェック
いまのあなたの傾向(ヴィクリティ)を簡易判定。
結果はPDFレポートで保存でき、日々のセルフケアのヒントもついてきます。
- Vata / Pitta / Kapha の割合を可視化
- 暮らしの整え方(食事・睡眠・運動)の要点
- そのまま PDF で保存・印刷 可能
※ 医療的診断ではありません。セルフケアの参考情報としてご活用ください。
カール・G・ユングは、人の心を「意識」と「無意識」から捉え、心理的態度(外向/内向)と心理的機能(感覚・直感・思考・感情)の組み合わせで傾向を説明しました。誰の中にも4機能はありますが、使い慣れた“主機能”と、補助・劣位の偏りが出ます。
1. 心理的態度:外向型/内向型
- 外向(Extraversion):外界との相互作用からエネルギーを得る。社交・行動が起点。
- 内向(Introversion):内的世界からエネルギーを得る。内省・概念化が起点。
2. 認識機能:感覚/直感
- 感覚(Sensing):五感・事実・具体。いま・ここ・実測を重視。
- 直感(Intuition):可能性・パターン・未来像。断片から全体や潮流を掴む。
3. 判断機能:思考/感情
- 思考(Thinking):論理・一貫性・基準。整合が取れるかで判断。
- 感情(Feeling):価値・調和・合意。自他の価値観と関係性を勘定。
4. タイプの組み合わせ(例)
- 外向的思考型:論理的で組織化が得意/意思決定が速い。
- 内向的直感型:洞察と長期構想に強み/新機軸の発見に向く。
- 外向的感情型:共感と調整に長ける/関係資本の活用が上手。
- 内向的感覚型:経験の蓄積と再現性に強い/堅実な運用を好む。
タイプ論の実用性と限界
タイプ論は傾向を捉えるレンズであって、ラベルではありません。人は状況・学習・加齢で変化しますし、単一タイプに固定されるものでもありません。資産形成に使う際は、自覚→補助→実装の順で活用し、「型に自分を合わせる」のではなく「自分に型を合わせる」前提を忘れないことが肝心です。
ユングのタイプ論と資産形成
タイプは「どの資産が向くか」より、どんなプロセスだと続けやすいかに効きます。下は相性と注意点の一例です(具体商品を推奨するものではありません)。
内向的思考型(Ti/Te寄り)
- 相性:ルールベース運用、インデックス積立、最適化・分散の設計。
- 注意:完璧主義で着手が遅れる。例外条項を増やしがち。
- 補助:「例外を作らない」明文化。小口テスト→拡張の順で動く。
外向的感覚型(Se寄り)
- 相性:実物の手触りがある領域(不動産、配当重視など)、定点観測。
- 注意:直近情報に引っ張られやすい。感情のピークで発注しがち。
- 補助:「翌日判断」ルールと、期日/価格/事象の三系統出口を固定。
内向的直感型(Ni寄り)
- 相性:長期テーマ・構造変化の仮説構築、成長株・新領域の少額分散。
- 注意:物語先行で根拠が薄くなりがち。
- 補助:「根拠3点(データ/期日/条件)」メモを作ってから発注。
外向的感情型(Fe寄り)
- 相性:ESG/ソーシャルインパクト枠+コアのインデックスで“芯”を保持。
- 注意:周囲やSNSの声に同調しやすい。疲弊で継続不能になりがち。
- 補助:感情ログ(強度1–10)を記録。閾値8以上は翌日に判断。
※他の組み合わせ(外向的思考、内向的感覚など)でも、考え方は同様に「相性/注意/補助」で設計できます。
自己診断→実装:1ページメモ
【SCENE】直近の投資判断(買付/見送り/リバランス) 【主に使った機能】感覚/直感/思考/感情(該当に◯) 【良かった点】その機能が効いた具体 【偏りのリスク】見落としや失敗パターン 【補助の一手】次回足す1ステップ(根拠3点/翌日判断/小口テスト 等) 【ルール更新】入口・サイズ・出口・例外の文言を1行更新
まとめ
タイプ論は、あなたがどのレンズで世界を見がちかを教えてくれます。資産形成では、そのレンズを活かし、足りないレンズを小さく補えば、ブレは減り、続けやすくなります。大切なのは「自分に合うプロセス」を設計すること。やり方選びの前に、まずは自分の認識と判断の癖を言語化してみてください。
あなたのタイプに合わせて、運用プロセスを設計し直す。
主機能を活かし、補助機能でバランスを取る“続く設計”へ。最初の1ページメモ作りからご一緒します。
※本記事は一般的な情報提供であり、特定の投資商品の推奨を目的とするものではありません。投資判断はご自身の責任で、必要に応じて専門家へご相談ください。



