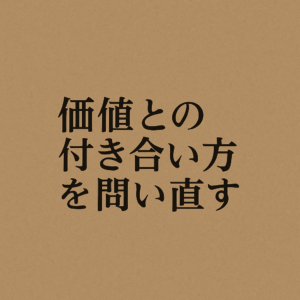その背景には、命を守りたいという自然な願いもあれば、人間中心の社会への違和感や、環境破壊への危機感もあるでしょう。一方で、クマがたびたび出没する地域では、現場の人たちが、日常の不安や緊張を抱えながら暮らしています。
子どもの通学路、畑や仕事場、家のすぐ裏山──ニュースの中では「どこか遠くの話」に見えても、その場所は誰かの生活圏です。
このテーマは、単に「クマをどうするか」という問題にとどまりません。
自分や家族を守りたい気持ちと、他の命を守りたい気持ちがぶつかったとき、私たちはどこに線を引くのかという、もっと根本的な問いでもあります。
遠くのクマと、目の前のクマ──距離が変える「正しさ」
多くの場合、「クマを殺すな」と語られているのは、あくまで「遠くのクマ」についてです。
画面越しに見ているのは、ニュース映像や写真、文字情報としての出来事であって、自分のすぐそばにいるクマではありません。
遠くのクマについて語るとき、私たちは比較的落ち着いて、倫理や理想を口にできます。
「命は平等だ」「人間の傲慢だ」「共存すべきだ」といった言葉が、スムーズに出てくるのもこの距離感ゆえかもしれません。
しかし、もし状況がこう変化したらどうでしょうか。
- ここ数週間、家のすぐ近くでクマの目撃情報が続いている
- 子どもの通学路やバス停付近で、何度もクマが確認されている
- 農作物の被害だけでなく、家屋のすぐそばにまで痕跡が見つかっている
- 見回りや追い払い、電気柵など、すでにできる対策はほぼ打ち尽くしている
こうした「目の前のクマ」の段階に入ったとき、同じ言葉を、同じ強さで言い切れる人はどれくらいいるでしょうか。
距離が変わると、「正しさ」の感触も変わってしまう──ここに、人間らしさと同時に、私たちの脆さがあらわれます。
理屈としての倫理と、本能としての「守りたい」がぶつかるとき
多くの人は、頭では「命はすべて大切だ」と考えています。
しかし現実には、私たちは無意識のうちに、命に優先順位をつけてしまうことがあります。
たとえば、次の二つの状況を想像してみてください。
- ニュースで見た、遠くの地域のクマと人とのトラブル
- 自分の子どもやパートナーが、クマと遭遇するかもしれない通学路や散歩道
このとき、どちらを強く守りたいと感じるかと問われれば、多くの人は後者を選ぶでしょう。
それはおそらく、「偽善」や「矛盾」というよりも、人間としてきわめて自然な反応です。
ただ、その自然な反応は、頭の中で掲げている倫理観とぶつかります。
「命は平等だと言いながら、自分の家族を優先してしまう自分」を前にしたとき、私たちは少し居心地の悪さを覚えるかもしれません。
ここで大切なのは、自分を責めることではなく、「自分の本音はどこにあるのか」を、静かに見つめ直してみることかもしれません。
きれいな言葉の陰に隠れた、守りたいもの・恐れていること・譲れないライン──それらを正直に認めることが、むしろ一貫した選択の出発点になります。
「誰がリスクを引き受けているのか」という視点
この問題を考えるうえで、もう一つ見落とされがちな視点があります。
それは、「誰が、どのリスクを、どのくらい引き受けているのか」という問いです。
「クマを殺すな」と語る人の中には、実際に出没地域で暮らしている人もいれば、遠く離れた場所からニュースを見て心を痛めている人もいます。立場はさまざまですが、
つぎのようなリスクや負担を、日々の暮らしの中で具体的に引き受けているのは、多くの場合、現場に暮らす人たちです。
・農作物や家屋が被害を受けるリスク
・人身事故が起こるかもしれないリスク
・見回りや監視、追い払いにかかる時間と労力
もちろん、「クマを守りたい」という思いそのものが間違っているわけではありません。
ただ、「発言している場所」と「リスクが集中している場所」とのあいだに距離があると、
現場からは「きれいな理想だけを求められている」と感じられやすい、というねじれが生まれます。
「誰がどこまで負担を引き受けているのか」という視点を一度挟むことで、
スローガンとしての共存ではなく、現実に根ざした対話の土台が見えてきます。
もし本当に「殺すな」を貫くのであれば、本来はそれに伴うコストも、どこかで分かち合われる必要があるはずです。
たとえば、
- 電気柵や餌付け防止などの対策に、社会全体でコストを負担する
- 人とクマの生活圏を分けるためのルールを、都市部も含めて一緒に考える
- 「危険な状況が続く地域に住む」という選択そのものを、どう支えるかを議論する
こうした「責任と負担の分かち合い」まで含めて考えないと、
スローガンとしての「共存」は、現場の人たちにとっては空虚に響いてしまいかねません。
一貫して「殺さない」を選ぶ人たちもいる──その覚悟とは
とはいえ、この世界には、どれだけ状況が厳しくなっても、可能な限り「殺さない」選択を貫こうとする人たちもいます。
その人たちは、単に理想を語るだけではなく、
- 柵や警報装置、ごみ管理など、具体的な対策を徹底する
- 行動範囲や生活スタイルを変えることも選択肢に入れる
- 「不安を抱えながら暮らす」という負担も、自分ごととして引き受ける
といったかたちで、自らの生活側にも大きな譲歩をしようとしています。
そこには、「命は平等だ」という信念だけでなく、
「その信念に沿って生きるために、自分は何を差し出せるか」という、かなり個人的で具体的な覚悟が伴っています。
理想を掲げることと、その理想を生きることのあいだには、いつも距離があります。
大事なのは、その距離をゼロにすることではなく、
「自分はどれくらいまで近づきたいのか」を、自覚的に選んでいくことなのかもしれません。
あなたはどこに線を引くのか──「問い」を自分に向けてみる
ここまで見てきたように、「クマを殺すな」という主張の背景には、さまざまなレイヤーが折り重なっています。
- 遠くから眺めるときに語りやすい理想
- 目の前に危険が迫ったときに揺らぐ本音
- 誰がリスクとコストを引き受けているのかという現実
- それでも理想を貫こうとする人たちの覚悟
これらを踏まえたうえで、最後に残る問いはきわめてシンプルです。
「自分だったら、どこに線を引くのか?」
自分や家族が直接のリスクにさらされる可能性が、
- ほとんどゼロに近いと感じられるとき
- 1%くらいあると想像されるとき
- 10%くらいあると感じ始めたとき
- 実際に被害が起きてしまったとき
そのたびに、あなたの中の「許容できるライン」は、どのように変化していくでしょうか。
私たちが向き合うべきなのは、「正しい答え探し」ではなく、
その変化していくラインの中にある、自分自身の価値観や恐れ、守りたいものの優先順位かもしれません。
クマの問題は、そのまま、「自分はいったい何を守りたい人間なのか」という問いでもあります。
その問いに丁寧に向き合うことは、野生動物との関係だけでなく、仕事やお金、人間関係、暮らし方の選び方にもつながっていきます。
「正しさ」と「本音」のズレを、一緒にほどいていく
頭で思い描く「こうあるべき」と、身体が望む「本当はこうしたい」のあいだには、しばしばズレが生まれます。
それは恥ずかしいことでも、未熟さの証でもなく、人が生きていくうえでごく自然な揺らぎです。
ただ、その揺らぎを見ないふりをし続けると、どこかで「自分の選択に納得できない」という違和感が積み重なっていきます。
逆に、そのズレを丁寧に言葉にしていくと、少しずつ、自分なりの一貫性が形になっていきます。
こうした「正しさ」と「本音」のあいだにあるズレに目を向けながら、
お金や仕事、暮らし方をふくめた人生全体の設計を問い直していくことが大切だと思います。
「自分だったら、どこに線を引くのか」という問いが、どこか心に残った方は、
一度ゆっくりと、その感覚を言葉にしてみませんか。
正解探しではなく、あなたの中にすでにある感覚や価値観を丁寧にすくい上げるところからご一緒します。