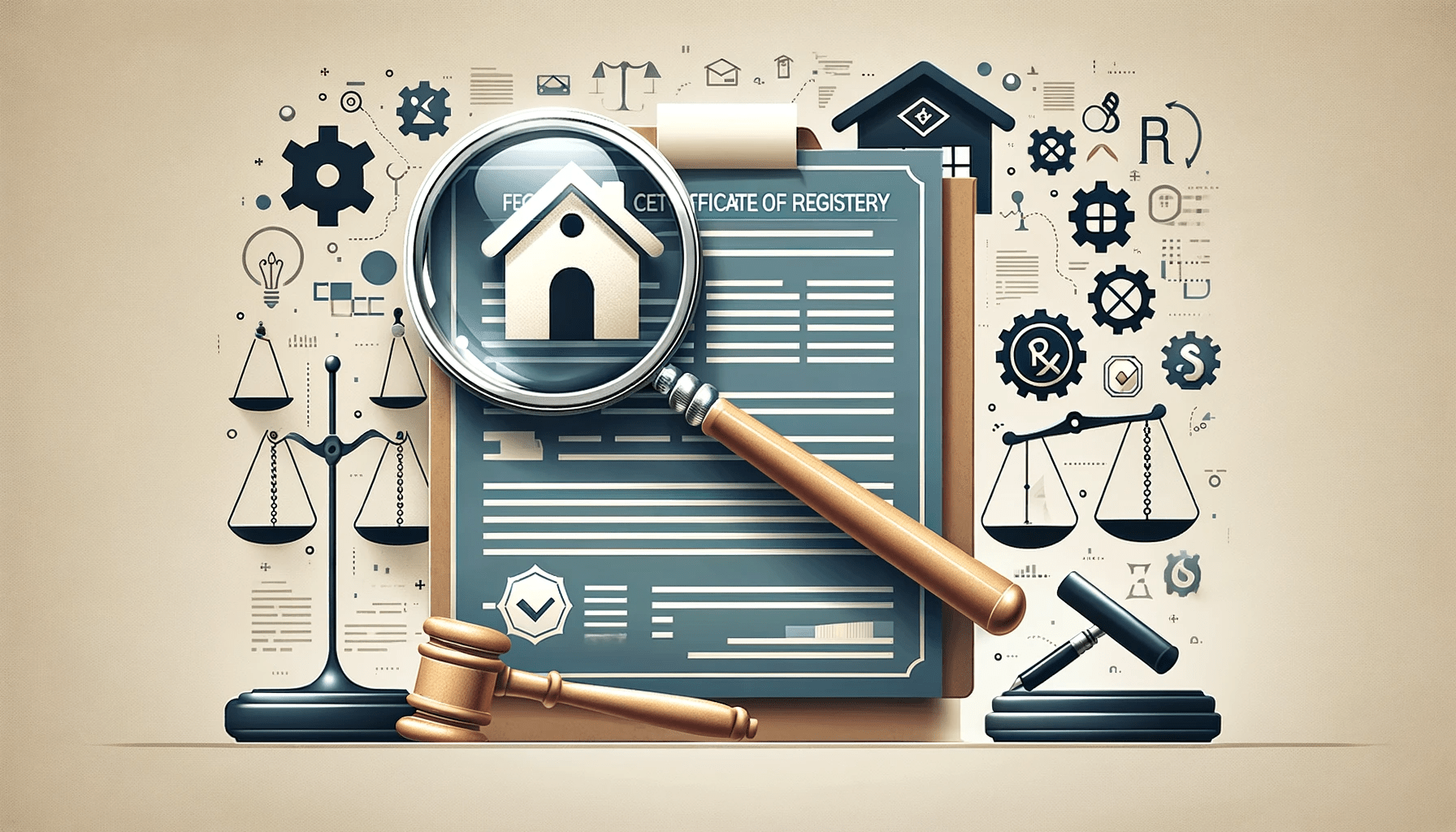
不動産登記手続きの原則
こんにちは!不動産に関する様々な情報を発信している[あなたのブログ名]です。今回は、不動産取引に欠かせない「不動産登記」について詳しく解説していきます。
1. 申請主義の原則
不動産登記は、基本的に当事者の申請に基づいて行われます。ですが、例外として裁判所や官公署の嘱託による場合もあります。さらに、表示の登記に関しては、登記官が独自の権限で実施することが許されています。
2. 共同申請の原則
登記を行う際、原則として登記権利者と登記義務者の双方が共同で申請する必要があります。ただし、特定の場面での単独申請も可能です。
3. 申請方法の三兄弟
- オンライン申請: インターネットを活用し、申請用のソフトやオンラインシステムを通じて行います。
- 出頭申請: 本人または代理人が直接登記所に足を運び、必要書類を提出します。
- 郵送申請: 必要な申請書類を郵送する方法。郵便での到着が申請の受付と見なされます。
4. 登記識別情報と登記済証の違い
新しい不動産登記法に基づく場合、登記が完了すると「登記識別情報」という符号が通知されます。これは過去の「登記済証」のようなもので、権利関連の登記を行う際に必要とされる情報です。
まとめ
不動産登記は、不動産取引を行う上で非常に重要なプロセスです。適切な知識を持ち、正確な申請を行うことで、スムーズな取引を実現しましょう。
不動産登記記録の構造を理解しよう!
不動産に関する重要な情報がまとめられている「登記記録」。この登記記録は、いくつかの区分に分けられており、それぞれ異なる情報が記載されています。今回は、その登記記録の構造と内容について詳しく解説します。
1. 登記記録の主要な区分
- 表題部: 登記記録の先頭に位置する部分で、一般的に物件の基本的な情報や土地・建物の種別、地番などが記載されています。
- 権利部: 表題部に続く部分で、不動産の権利関係についての詳細が記述されます。さらに、この権利部は以下の二つに細分化されています。
- 甲区: 主に物権に関する情報、たとえば所有権や担保権などの内容が記載されます。
- 乙区: 使用権や賃貸借に関する情報など、物権以外の権利情報が詳細に記述される場所です。
※詳細な情報配置は、提供された図を参照してください。
2. 従来の不動産登記簿
現在のコンピュータ化されたシステム以前、不動産の情報は「不動産登記簿」という紙の簿に記録されていました。この従来の不動産登記簿には、大きく「土地登記簿」と「建物登記簿」の2種類が存在していました。
- 土地登記簿: 土地の情報が地番順に一筆ごとに記録されているもの。
- 建物登記簿: 建物の情報が1棟ごとに所在地番順に記載されているもの。
この従来の方式は、コンピュータ化以前の登記所での主要な手法であり、閉鎖登記簿としても参照されることがあります。
図表5‐4
| 表示の登記 (表題部) |
土地や建物の物理的概要が記録されている。 土地登記記録:所在、地番、地日、地積など 建物登記記録:所在、家屋番号、種類、構造、床面積など |
|
| 権利の登記 (権利部) |
甲区 | 所有権に関する事項が記録されている。 所有権の保存、移転など、所有権に関する差押え、 共有物の分割禁止などの処分の制限など |
| 乙区 | 所有権以外の権利に関する事項が記録されている。 | |
区分所有建物の登記記録は、図表5-5のとおり1棟の建物の全体を表示した表題部と、専有部分の表題部、権利部の甲区および乙区で構成されている。
※1棟の建物の登記事項に変更があった場合は、その棟に属する他の区分所有建物についても同様の登記としての効力がある。
図表5-5
| 1棟の建物の表題部 | 1棟の建物の表示 | 1棟の建物の物理的概要が記録されている。 所在、建物の番号、構造、床面積など |
|
| 敷地権の目的である土地の表示 | 1棟の建物の敷地の物理的概要が記録されている。 所在、地番、地日、地積など |
||
| 専有部分の 建物の表題部 | 専有部分の建物の表示 | 専有部分の建物の物理的概要が記録されている。 家屋番号、建物の番号、種類、構造、床面積など |
|
| 敷地権の表示 | 専有部分に係る土地利用権の概要が記録されている。敷地権の種類、敷地権の割合など | ||
| 権利の登記 (権利部) | 甲区 | 専有部分の所有権に関する事項が記録されている。 所有権の変動と原因、差押えなど | |
| 乙区 | 専有部分の所有権以外の権利に関する事項が記録されている。 抵当権、賃借権など |
||
不動産取引や資産管理の際、登記記録は欠かせない重要な資料となります。その構成や内容を理解しておくことで、よりスムーズに取引や管理を進めることができるでしょう。
登記記録の公開とその取得方法
不動産取引や資産管理において、重要な情報源となるのが登記記録です。その登記記録は公開されており、様々な方法で取得できます。以下にその詳細を説明します。
1. 登記事項証明書の取得
- この証明書は、登記記録に記録されている事項を証明する公的な書面です。
- 登記所に手数料を納付することで、誰でもこの証明書の交付を請求できます(不動産登記法119条1、2項)。
- 証明書には公的証明のため、登記官の印が押されます。
- また、この証明書は郵送での取得も可能です。
- さらに、ある登記所の管轄外の不動産に関する情報もその登記所で請求可能です(同法119条5項)。
2. 登記事項要約書の取得
- これは登記記録の概要を示す書面です。
- 公的文書としての証明力を持たないため、登記官の証明印は押されません。
- この要約書は、原則として管轄の登記所の窓口でしか取得できません。
3. 閉鎖登記記録の取得
- 閉鎖された登記記録については、登記簿謄抄本の請求や閲覧が必要です。
4. 請求の際の情報提供
- 土地に関する請求の際は「地番」、建物に関する請求の際は「家屋番号」を記載します。
- 地番や家屋番号が不明な場合は、公図や住宅地図の参照、または所有者名などを元に申請が可能です。
5. 注意事項
- 登記記録の内容は、必ずしも実際の状況や権利関係を反映しているとは限りません。
- 例として、現状が宅地であるのに、地目が畑として登記されている場合や、所有者名が誤って記載されている場合があります。
- そのため、登記記録の情報を元に行動する際は、他の資料との照合や十分な調査が必要です。
登記記録は非常に重要な情報源となりますが、その内容には十分な注意が必要です。適切な情報を取得し、必要な調査を行うことで、不動産取引や資産管理を安全に進めることができます。
登記事項証明書の見方
不動産取引や権利関係の確認の際、登記事項証明書は欠かせない公的な文書となります。その見方を理解することで、不動産の物理的な変動や権利関係の変動を的確に把握できます。以下に、登記事項証明書の見方を詳細に解説します。
① 表題部
- 土地・建物の表示: 登記事項証明書の最初に記載される部分です。
- 地積・床面積の変動: 過去から現在にかけての土地や建物の面積の変化が表示されます。
- 変動原因: 地積や床面積の変動の原因が明記され、例えば分筆、合筆、錯誤や新築、増築などとして表示されます。
- 不動産番号: 一筆の土地や一個の建物を識別するための番号や記号が記載されます。この番号を利用することで、詳しい情報の記載を省略できます。
② 権利部
- a) 甲区
- 所有権の情報: ここには、所有権に関連する情報が詳細に記載されます。
- 登記の目的: 所有権移転や差押えなどの目的が記載されます。
- 原因: どのような原因で変動が生じたか、例えば売買、相続、代物弁済などとして記されます。
- 共有者の情報: 共有の場合、各共有者の持分が明記されます。
- 現在の所有者: 順位番号が最も大きいものが現在の所有者を示します。その他の小さい順位番号は、過去の所有者の変動を示しています。
- 所有権の情報: ここには、所有権に関連する情報が詳細に記載されます。
- b) 乙区
- 所有権以外の権利の情報: ここには、抵当権や地役権などの権利関係が記載されます。
- 登記の目的: 抵当権の設定や地役権の設定、賃借権の設定などが記載されます。
- 原因、債権額、極度額: その権利を設定するための原因や、債権の金額、最大の金額などが記載されます。
- 共同担保目録番号: 共同での担保に関する情報が記載されます。
- その他の情報: その他の特約や条件が記載されます。
- 所有権以外の権利の情報: ここには、抵当権や地役権などの権利関係が記載されます。
登記事項証明書は、一見複雑に見えるかもしれませんが、上記のように分類・解析することで、不動産の権利関係を正確に把握することができます。取引や権利確認の際は、この証明書をしっかりと確認し、適切な判断を行うことが求められます。
次回も不動産取引を安全かつ円滑にしていくために必要なことについてです。
ではまた。




