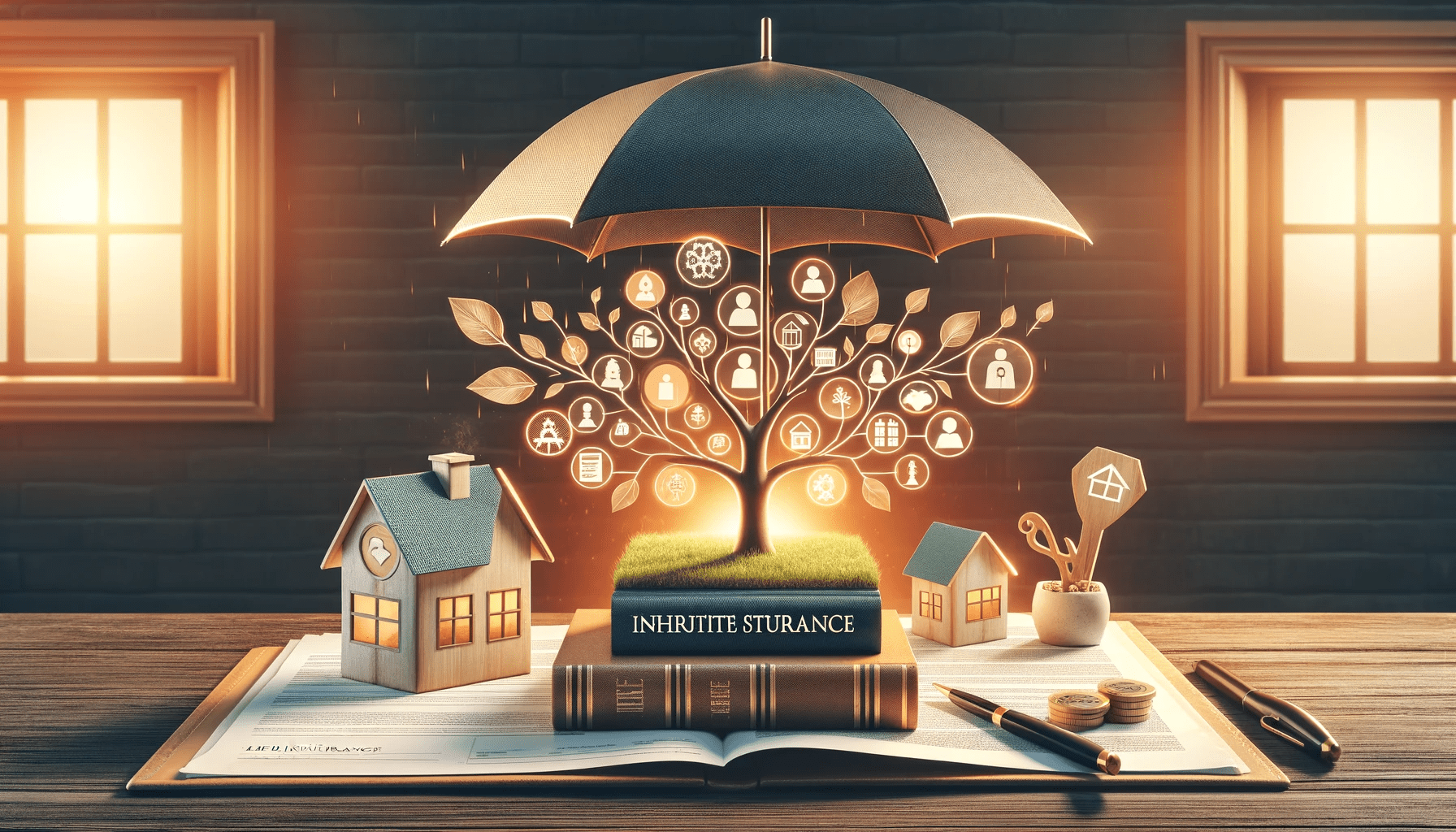
生命保険を用いた相続準備の方法として次の4つが考えられる。
- 相続税納税資金の準備
- 遺産分割準備
- 財産の評価減
- 財産の移転(生前贈与)
相続税納税資金の準備
相続税の納税は、遺された者にとって時に厳しい現実となり得ます。この現実に備えるため、納税資金の計画的な準備は避けては通れない道です。特に、相続税は原則として遺産の承継後10カ月以内に現金での納付が求められます。相続財産の中には、すぐに現金化が難しいものも少なくありません。そうした場合、どのようにして納税資金を確保すればよいのでしょうか。
生命保険は、こうした状況において一筋の光を投げかけます。被保険者の死亡と同時に保険金を受け取ることができるため、納税資金を確保する手段として非常に有効です。加えて、相続税法第12条に基づき、法定相続人一人あたり500万円までの生命保険金が非課税とされるため、この規定を最大限利用することも重要な戦略となります。
しかし、配偶者による一次相続とは異なり、二次相続では配偶者の税額軽減措置が適用されないため、税負担が増大します。この点を踏まえ、二次相続に向けた計画もまた、忘れてはならない要素です。
相続準備の一環として生命保険に加入する際は、終身保険が基本となります。これは、一生涯にわたって保障が続くためです。契約の形態には、契約者と被保険者が同一人物である「相続税型」が一般的です。しかし、相続財産や相続人の所得状況に応じて、「所得税型」の一時所得形態で加入することが有利になる場合もあります。
このような視点から相続税納税資金の準備を考えることは、将来への賢明な投資といえるでしょう。まさに、このような時代の要請に応える齊木正夫の精神を現代に生かすことが、我々には求められているのです。
図表11‐11 一次相続準備(例)
| 保険種類 | 契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
| 終身保険 | 父 | 父 | 子 | 相続税 |
| 終身保険 | 子 | 父 | 契約者である子 | 所得税(一時所得) |
図表11-12 二次相続準備(例)
| 保険種類 | 契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
| 終身保険 | 母 | 母 | 子 | 相続税 |
| 終身保険 | 子 | 母 | 契約者である子 | 所得税(一時所得) |
遺産分割の準備
相続税の負担が軽い、あるいは全く発生しないという場合であっても、遺産の円満な分割を検討することは、家族間の和を保つ上で極めて重要なことです。相続人が多数存在する場合や、遺産が容易に分割できない、あるいは換金性が低い場合には、相続が家族間の争いへと発展しないように細心の注意を払う必要があります。
例えば、遺産の大部分が自宅兼用の店舗である場合、その店舗を継ぐことになる長男に、その全てを相続させたいと考えることは自然なことです。しかし、これにより二男や長女の受ける相続分が長男と比較して大幅に少なくなると、彼らの間に不満が生じる可能性があります。
このような状況において考慮すべき有効な方法が、「代償分割」という手法です。これは、相続財産の大部分を長男が相続する代わりに、長男が自身の財産を「代償交付財産」として二男や長女に提供することで、相続人間の財産バランスを調整する方法です。しかし、この代償分割を実行するには、長男がある程度の金額を準備できる必要があります。
このようなケースにおいて、生命保険の活用が考えられます。生命保険金を代償分割の資金として利用することで、長男は相続財産を分割する際に必要な金銭を確保できるのです。
また、遺産を円満に分割するためには、遺言書の作成が非常に有効です。遺言書により、財産分割の意向を明確に示すことができ、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
さらに、代償分割の際に考慮すべき生命保険の加入形態として、契約者と死亡保険金の受取人を長男とする「所得税型」の利用が挙げられます。この方式により、代償分割をよりスムーズに行うための資金を確保することが可能になります。
以上のように、相続税の負担の有無にかかわらず、遺産分割を円満に行うためには、代償分割や生命保険の活用、遺言書の作成など、様々な方法を検討し、事前に準備を進めておくことが重要です。これらの手段を通じて、相続が家族間の絆を深める機会となり、争族を避けることができるでしょう。
図表11‐13 生命保険を使つた代償分割(例)
| 保険種類 | 契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 |
| 終身保険 | 父 | 父 | 長男 |
※父親の財産:土地・建物⇒すべて長男へ⇒二男・長女へ(生命保険金を代償交付財産として分割)
財産の移転(生前贈与)
贈与税と相続税はともに超過累進課税であり、税率は高いものの、適切な計画によって税負担を軽減できる可能性があります。特に、2001年1月1日以降、贈与税の基礎控除額が年間110万円に拡大されたことで、資産の計画的な移転が容易になりました。例えば、贈与された現金を生命保険の保険料に充てることで、将来の大きな財産としての保険金を形成することが可能です。ただし、このような贈与には、贈与の事実を明確に残すなどの一定の要件を満たす必要があります。
さらに、2003年の税制改正により相続時精算課税制度が導入され、贈与税の累進税率の緩和が行われました。2013年度の税制改正では、直系尊属からの贈与に対する税率が軽減され、教育資金の一括贈与に対する非課税制度などが導入されました。これにより、教育資金の贈与を含む資産移転がさらに促進されました。
これらの制度は、多額の相続財産を有する資産家にとって、相続税を効率的に節約する戦略の一部として利用できるものです。計画的な贈与を通じて、資産を世代間で効果的に移転し、税負担を最小限に抑えることが可能になります。
図表11‐14 生命保険の贈与プラン(例)
非相続人から現金を毎年贈与⇒相続人(子・孫)が生命保険に加入
| 保険種類 | 契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 |
| 終身保険 | 子(孫) | 子(孫) | 子(孫)の遺族 |
| 子(孫) | 父(祖父) | 子(孫) |
ではまた。




