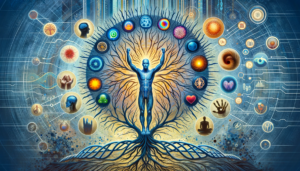いまの「暮らしの立ち位置」を見える化する──パーソナル・バランスシートという考え方
ライフプランを考えるとき、私たちはどうしても「毎月の収支」や「今年いくら貯められるか」といったフロー(流れ)に意識を向けがちです。
しかし、本当に知りたいのは、
- いまこの瞬間、自分の資産と負債はどんなバランスにあるのか
- その構造は、これからの暮らしや人生設計にとって健全と言えるのか
という「ストック(蓄え)の全体像」です。
そのスナップショットを一枚の表に落とし込んだものがバランスシートであり、それを個人に適用したものがパーソナル・バランスシートです。
年間キャッシュフロー報告書やキャッシュフロー表を作成すると、年次ごとの現金収支は把握できます。ですが、それだけでは、資産・負債の全体像やポートフォリオの偏りまでは見えにくいのが実情です。
特に、不動産や株式に評価損が出ている場合や、住宅ローンなど多額の負債を抱えている場合は、キャッシュフロー表だけで問題点を発見するのは難しくなります。そこで役に立つのが、バランスシートによる「静止画」の把握です。
本記事では、資産・負債・ポートフォリオの状況を見える化するためのバランスシートの構造・作成方法・留意点・分析の視点を、事例を交えながら解説していきます。
なお、キャッシュフロー表の作成については、すでに公開している「ライフイベント表とキャッシュフロー表」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。また、ライフプラン作成時に活用できる各種データはこちらにまとめています。
パーソナル・バランスシートの基本構造
バランスシートの基本となる公式は、とてもシンプルです。
(総)資産 = 負債 + 純資産
または、
純資産 = (総)資産 − 負債
法人の貸借対照表と異なり、個人のバランスシートには出資による「資本」はありません。そのため、資産から負債を差し引いた残りがプラスであれば、それがそのまま純資産になります。逆にマイナスの場合は、資産と負債のバランスが崩れている「純負債」の状態です。
1. 資産の方が多い場合
| 資産 | 負債および純資産 |
| 負債 | |
| 純資産 | |
| 資産合計 | 負債と純資産の合計 |
2. 負債の方が多い場合(純負債)
負債の総額が資産合計を上回る場合、構造の把握のために「純負債」という見方を使うこともあります。
| 資産および純負債 | 負債 |
| 資産 | |
| 純負債 | |
| 資産と純負債の合計 | 負債と純資産の合計 |
「資産が多いから安心」「負債が多いから危険」と単純に判断するのではなく、構造としてどうなっているかを一度フラットに見える化する。そのための「型」として、この公式を捉えておくと役に立ちます。
数字の裏側(リスク・感度・逆算)まで1画面で可視化。
未来の選択を「意味」から設計します。
- モンテカルロで枯渇確率と分位を把握
- 目標からの逆算(必要積立・許容支出)
- 自動所見で次の一手を提案
ライフプランと資産ポートフォリオの関係
資産と一口に言っても、その中身はさまざまです。
- 現金・預金
- 株式・債券・投資信託
- 土地・建物などの不動産
- キャッシュバリューのある生命保険・個人年金
- 確定拠出年金・変額年金などの年金資産 など
これらのアセット(資産)クラスは、
- インカムゲイン:利子や配当、家賃収入などの「定期的な収入」
- キャピタルゲイン:売却による値上がり益
という2種類のキャッシュフローを生み出します。そして、こうした資産の組み合わせ全体をポートフォリオと呼びます。
ライフプランとの関係で考えると、次の3つのポートフォリオを区別しておくと整理しやすくなります。
- ①総資産ポートフォリオ:すべての資産クラスを含めた全体構成
- ②マネーポートフォリオ:現金・預金+株式・債券・投資信託など金融資産の構成
- ③証券ポートフォリオ:株式・債券・投資信託など証券部分の構成
バランスシートⅠ(構造のイメージ)
| 資産 | 負債および純資産 |
現金など
投資資産
使用資産
| 負債
|
| 負債合計 | |
| 純資産 | |
| 資産合計 | 負債と純資産の合計 |
ライフプランは「いつ・いくら必要か」という時間軸の設計ですが、バランスシートは「いま、何をどう持っているか」という構造の設計です。この二つを行き来しながら考えることで、資産配分と人生の優先順位が少しずつ揃っていきます。
バランスシート作成方法と3つの資産区分
個人のバランスシートには、厳密な「正解のフォーマット」はありません。大切なのは、自分と家族にとってわかりやすい形で構成しておくことです。
たとえば、法人にならって、
- 1年以内に換金できるものを「流動資産・流動負債」
- 1年を超えて保有するものを「固定資産・固定負債」
といった区分を用いても構いませんし、米国でよく用いられる次の3区分にまとめる方法もシンプルで扱いやすく、おすすめです。
a)現金など
現金および現金同等物(価値がすぐ現金化できるもの)であり、流動性の高い資産です。
- 現金・預金
- 養老保険・個人年金など、キャッシュバリュー(解約返戻金)のある生命保険
このうちの一部は、「不時の出費」に備える緊急資金として位置づけられます。
b)投資資産
将来の資産形成を目的として保有する資産です。
- 株式・債券・投資信託
- 確定拠出年金・変額年金
- 賃貸用不動産・コモディティ(商品)など
流動性の高い変額年金であれば現金に分類することもできますし、逆にキャッシュバリューのある外貨建て個人年金を投資資産とみなすことも可能です。賃貸アパートを所有している場合は、投資資産として扱うのが一般的です。
c)使用資産
日常生活のために実際に使用している資産です。
- 住宅・土地
- 自家用車
- 家財など
ただし、将来的に住宅を売却して住み替える予定がある場合などは、部分的に投資資産の性格も持ちます。負債に関しては、クレジットカードのキャッシング残高なども流動負債として計上する必要があります。
バランスシートと資産評価・負債の意味
バランスシートにおける資産評価は、原則として「時価評価」で考えるのが基本です。特に次のような資産は、評価方法に注意が必要です。
1. 土地などの不動産
不動産については、近隣の取引事例や路線価などを参考に、できるだけ現実的な時価を把握する必要があります。不動産の効率的な活用については、「不動産を効率的に活用する」も参考になります。
2. 生命保険など
養老保険・終身保険・個人年金保険など、資産性のある生命保険については、解約返戻金(キャッシュバリュー)を時価として記入します。生命保険全般については、「リスクをマネジメントする」のカテゴリで詳しく解説しています。
3. 株式など金融資産
株式や投資信託などは、評価日の終値をもとに時価評価します。中高年期以降であれば、相続税評価額をあらかじめ試算し、将来の相続税額のイメージを持っておくことも大切です。金融資産運用の基本については、「マネープラン・ガイダンス」を参照してください。
4. 負債の意義
借入は一見「マイナス」のイメージが強いですが、返済可能な範囲の負債は、資産形成の原動力のひとつにもなり得ます。重要なのは、
- 負債から生じる元本返済と利息支払いのマイナスキャッシュフローを
- その負債によって生み出される資産や収益が上回れるかどうか
という視点です。そのうえで、資産と負債のバランスをどのように整えるかを検討します。将来のキャッシュフローを慎重にシミュレーションし、借入れや繰上げ返済のタイミングを判断していくことが求められます。
バランスシートの分析と見直しポイント
パーソナル・バランスシートを分析するとき、特に注意したいのは次の2点です。
- ライフプランとリスク許容度が前提になっていること
- 資産の「換金性・安全性・収益性」のバランスを見ること
そのうえで、次のようなチェックポイントを確認してみましょう。
① ライフプラン上の目標達成に見合った構成になっているか?
将来の教育費・住宅・老後資金といったライフイベントに対して、資産構成は現実的かどうか。「ライフプランを安易に作成すると資産が目減りする!?」なども参考になります。
② 預貯金が多すぎないか?
元本保証の安全性を重視するあまり、収益性が極端に低くなっていないか。インフレや円安による貨幣価値の変化に対して、どの程度のリスクを抱えているかを確認します。
③ 不動産の割合が大きすぎないか?
土地価格の二極化やデフレ傾向の中で、所有不動産の資産価値が目減りし、換金性・収益性が乏しくなっていないか。
④ 株式などリスク資産が多すぎないか?
収益性を優先するあまり、ご自身のリスク許容度を明らかに超えていないか。価格変動に精神的に耐えられるかどうかも含めてチェックします。
⑤ リスクは適切に分散されているか?
預金の分散(預金保険機構の範囲内かどうか)、株式・債券・不動産など資産クラスの分散、国内と海外の分散などを確認します。
⑥ 相続や遺産分割を意識した構成になっているか?
中高年者の場合、公平性や各家族の事情を踏まえながら、遺産分割が現実的に行える構成になっているかどうかも重要な視点です。
事例①:資産と負債の内容から見える構図
ここからは、実際のモデルケースをもとに、バランスシートの読み取り方を確認していきます。
【モデルケースⅠ】 資産と負債の内容
| 家族構成 |
|
| 税引き前年収 |
|
| 妻の収入 |
|
| 保有資産(2013年12月31日現在) | |
| |
| 負債 | |
| |
バランスシート化する
| 資産 | 負債および純資産 |
現金など 270万円
投資資産 30万円
使用資産 2,600万円
| 負債
|
| 負債合計 1,760万円 | |
| 純資産 1,140万円 | |
| 資産合計 2,900万円 | 負債・純資産合計 2,900万円 |
資産のうち、キャッシュフロー表の「貯蓄残高」に現れるのは、現金など+投資資産=300万円の金融資産部分のみです。しかし、バランスシートとして並べてみると、金融資産300万円に対して純資産は1,140万円あることが、一目でわかります。
その要因は、相続により取得した土地(評価額1,000万円)の存在です。一方で、建物だけを見ると、評価額1,500万円に対して住宅ローン残債が1,700万円と、負債の方が大きい点には注意が必要です。
ただし、土地部分も含めた不動産全体の評価額(合計2,500万円)を考慮すると、不動産価格が大幅に下落しない限り、すぐに問題になる状況ではないと判断できます。このケースでは、「早急な大規模見直しは不要だが、資産に占める不動産割合や、金融資産の中での預貯金偏重には意識を向けたい」という結論になるでしょう。
バランスシートに「問題のサイン」が出ているケース
バランスシートを作成した際、次のような状態であれば、何らかの対策を検討するサインと考えられます。
- ① 資産の内訳に偏りが大きい
- ② 負債額が大きく、純資産が少額、あるいはマイナスになっている
例:マンション購入後、教育費増加で純資産がほぼゼロに近いケース
- 数年前にマンションを購入
- 子どもの教育費など支出が増加
| 資産 | 負債および純資産 |
現金など 150万円
使用資産 2,100万円
| 負債
|
| 負債合計 2,230万円 | |
| 純資産 20万円 | |
| 資産合計 2,250万円 | 資産合計 2,250万円 |
純資産がほぼゼロに近い状態であれば、「一気に解決する特効薬」はありません。現実的には、
- 貯蓄を増やすペースを上げる
- 繰上げ返済などで負債を少しずつ減らす
といった方針を立て、数年単位で純資産を積み上げていく必要があります。自営業者の場合は、事業の変動リスクも加わるため、より慎重な判断が求められます。
なお、純資産がプラスで、今後大きな新規借入れの予定がなく、安定した事業収入も見込めるのであれば、「数字としては心許ないが、直ちに危機的というわけではない」といった見立ても可能です。大切なのは、資産合計に対する純資産の割合を意識し、構造を時間をかけて改善していく姿勢です。
改善前後のバランスシート比較:負債圧縮という選択
次に、自営業者の例を用いて、「負債の整理・繰上げ返済」によってバランスシートがどう変わるかを見てみましょう。
改善策実行前のバランスシート
| 資産 | 負債および純資産 |
現金など 800万円
投資資産 200万円
使用資産 4,000万円
| 負債
|
| 負債合計 4,800万円 | |
| 純資産 200万円 | |
| 資産合計 5,000万円 | 負債・純資産合計 5,000万円 |
ここでは、
- 現預金から400万円、MMFから100万円の合計500万円を用いて
- 自動車ローンとカードローンを完済し、その残りで事業用ローンの繰上げ返済を行う
という改善策を実行したと仮定します。
改善策実行後のバランスシート
| 資産 | 負債および純資産 |
現金など 300万円
投資資産 200万円
使用資産 4,000万円
| 負債
|
| 負債合計 4,300万円 | |
| 純資産 200万円 | |
| 資産合計 4,500万円 | 負債・純資産合計 4,500万円 |
純資産の金額は200万円で変わっていませんが、資産合計が5,000万円から4,500万円に減ったことで、
- 純資産比率:4% → 4.44%に改善
- 高金利負債(自動車ローン・カードローン)がなくなり、事業用ローンも圧縮
という効果が生まれています。数字としては小さな変化に見えるかもしれませんが、毎月のキャッシュフローの健全化という意味では大きな一歩です。
デフレ・低インフレ環境では、「資産を増やす」ことだけに頼らず、負債を減らす方向で計画を立てる方が、現実的で再現性の高い改善策になる場面も多くあります。
連年バランスシートで「未来の自分の姿」を先に見ておく
単年度のバランスシートが作成できたら、そこから一歩進めて、数年先のバランスシートをシミュレーションすることもできます。これを「連年バランスシート」と呼びます。
各資産に予想収益率をかけ、負債の返済予定を反映することで、
- 5年後・10年後の自分の資産構造はどうなっているか
- いまのペースのままで、本当に思い描いているライフプランに届くのか
といった問いに、具体的なイメージを持つことができます。
55歳会社員Bさんの事例
ここでは、55歳会社員Bさんのバランスシートが、5年後の退職時にどう変化するかをシミュレーションした例を簡単に紹介します。
前提条件(55歳時点)
- 現金など 2,000万円(預金1,350万円+生命保険現金価値650万円)
- 投資資産 200万円(国債100万円+投資信託100万円)
- 使用資産 2,570万円(住宅・土地2,500万円+自動車50万円+家財20万円)
- 住宅ローン残高 1,300万円
- 5年後の60歳時に退職金手取り2,000万円を受け取る予定
- 預金・国債は年率1%上昇、投資信託は年率3%上昇
- 住宅・土地・自動車・家財は年率3%下落
- 住宅ローンは5年後までに元金が1,000万円減少
55歳時のバランスシート
| 資産 | 負債および純資産 |
現金など 2,000
投資資産 200
使用資産 2,570
| 負債
|
| 負債合計 1,300 | |
| 純資産 3,470 | |
| 資産合計 4,770 | 負債と純資産合計 4,770 |
60歳退職時のバランスシート(シミュレーション)
| 資産 | 負債および純資産 |
現金など 4,180
投資資産 221
使用資産 2,207
| 負債
|
| 負債合計 1,000 | |
| 純資産 5,608 | |
| 資産合計 6,608 | 負債と純資産合計 6,608 |
このように、連年バランスシートを作成しておくことで、
- 現状の資産配分のままで、退職時にはどの程度の純資産になりそうか
- 住宅ローンの繰上げ返済や、投資配分の見直しをどこで行うべきか
といった検討を、「現実味のある数字」を伴って行うことができます。「なんとなく不安」から一歩進んで、「どこをどう動かせばいいのか」が見えやすくなるのが、この作業のメリットです。
おわりに──数字をそろえながら、「自分の納得」とも対話する
パーソナル・バランスシートは、単なる数字の一覧表ではありません。そこには、
- これまでどんな選択をしてきたのか
- 何を優先し、何を後回しにしてきたのか
- これからどんなバランスで生きていきたいのか
といった、あなたのライフストーリーが反映されています。
バランスシートを作成し、連年シミュレーションまで行ってみると、「思ったより土台はしっかりしている」「意外なところに偏りがある」「負債との付き合い方を見直したい」など、さまざまな気づきが生まれてきます。
大切なのは、その気づきを責める材料にするのではなく、「ここからどう整えていくか」を考える出発点にすることです。数字と向き合うことは、自分のこれまでの選択と向き合うことでもあります。
一度、あなた自身のバランスシートを作成してみてください。そして、必要であれば、専門家との対話の材料としても活用してみてください。数字の裏側にある「自分なりの納得感」と折り合いをつけながら、これからのライフプランを描いていく。そのための一つのツールとして、バランスシートを役立てていただければ幸いです。